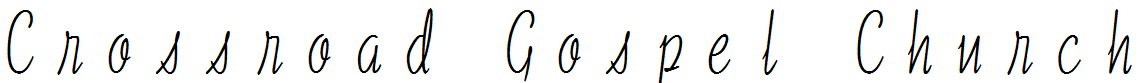
![]()
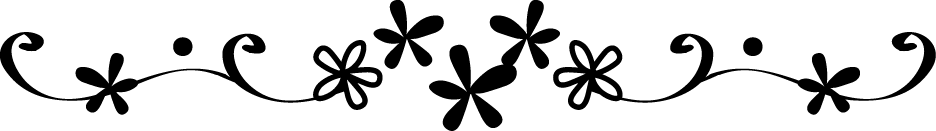
2019年10月1日、玄武書房より全国発売されました。アマゾンにて購入いただけます。画像をクリックすると購入ページに飛びます。
以下、礼拝メッセージの要約と共に音声もお聴き頂けます。
2026年2月15日礼拝メッセージ マルコ3:31~35 「神の御心」 ![]() メッセージは14分過ぎからです。
メッセージは14分過ぎからです。
2026年2月8日礼拝メッセージ マルコ3:20~30 「マリヤもか」 ![]() メッセージは13分20秒からです。
メッセージは13分20秒からです。
食事する暇も無かったとは…ワンオペの美容室ならまだしも、使徒だけでも12人いたのに交代で休憩も取れなかったのなら異常な状態だ。
それで、マリヤ達は「イエスは気が狂った」と思って連れ戻しに来た(21)。これは大問題である。と言うのは、律法学者達も「彼は、ベルゼブルに取りつかれている」(22)と中傷したが、それは「気が狂った」という意味の当時の慣用句であるからだ。因みに、ベルゼブルとは何者か。オカルト系の本では、悪魔の一人とかサタンとされているが、ユダヤ教の文献では、サタンはベルゼブルと呼ばれてはいない。だから「悪霊共のかしらによって悪霊共を追い出している」という中傷とは別の意味(先述の慣用句)なのである。更に因みに、主は反論として「サタンがどうしてサタンを追い出せようか」(23)と言うが、サタンは複数存在しない。ただ、悪霊共はサタンの一味であり、その働きは総じてサタンの働きであるゆえ、悪霊をサタン呼ばわりする事はある。だから主の反論の趣旨は「悪霊が別の悪霊を追い出すなら分裂だ、滅びる」(24~25)という事なのである。
それで「ベルゼブルに取りつかれている(気が狂っている)」に対する反論が28~29節である事は30節から明らかだが、28節は「どんな罪を行っても構わない」という意味ではない。ただ「悔い改めたなら赦される」という事だ。しかし、聖霊をけがすなら決して赦されない。何故なら聖霊は悔い改めに導くお方だからである。それをけがす=悔い改めを拒む=永遠に赦されない=とこしえの罪に定められる=地獄という事になる訳である。そして、あろう事か、マリヤ達も「イエスは気が狂った」と思っていた。主の反論によればそれは「聖霊をけがす事」だ。そのままでは非常にまずい(神の家族になれない)事になる。事実、そのあと主はマリヤを否定した(33~34)。勿論のちには、マリヤ達も悔い改めてイエスを主としたから幸いだが。だから、聖霊による真実な悔い改めがいかに大切かという事だ。
この様に、悔い改めへと促す聖霊に従うなら幸いなのである。信仰の向かう方向を、いつも聖霊によって天へと方向を修正(方向転換)させて頂ける様に導かれて歩もう。
2026年2月1日礼拝メッセージ マルコ3:7~19 「退く王」 ![]() メッセージは13分頃からです。
メッセージは13分頃からです。
人々に福音を伝える為にわざわざ出て来たはずなのに主は、退かれた。マルコは、そこに注目する。では、主が退いた理由は何か。まず、パリサイ人達が主への殺意をむき出しにし始めたからだ(6)。が、まだ十字架の時ではない。もう一つは、大勢の人が押しかけて来たから。将棋倒しを避ける為に小舟に身を引いた(7~10)。そして、悪霊が余計な事を言うから身を隠そうとした(11~12)。全ては、救いの計画の完成の為に、退かざるを得なかったという事だ。更に、山に登ったが、それは祈りや休息の為が常で、言わば退いたという事だが、今回は12使徒の任命というミッションがあった。余談だが、ヤコブとヨハネにはボアネルゲというあだ名を付けた。二人に同じ名前だと呼ぶのに困ると思うが、あだ名は霊的性質の指摘であって日頃の呼び名ではないのだろう…例えば主はペテロを、いつもシモンと呼んだ。
さて驚くのは、主はユダをも使徒に「望んだ」という事だ(13)。恐らく、ゲッセマネでの祈りの様に「願わくは、この杯を取り除いて…しかし御心の通りに…」と苦しい祈りの末に選んだのではないか。救いの計画の完成の為にだ。ならば15節はどうか。主は悪霊を滅ぼす為に来たのではないはずだが、弟子達には積極的に悪霊を追い出させるのは何故か。そもそも、悪霊に取りつかれた人がそんなに沢山いたのか。日本なら偶像だらけだが、仮にも真の神を信じる人々の中に…。
マルコ16章に「たとえ毒を飲んでも害を受けず」とあるが、信じて実行した人はいないだろう。問題は毒とは何かだ。クリスチャンを霊的に滅ぼす「毒」それは偽りの教えだ。だから、悪霊を追い出す(偽りを跳ね返す)為に、使徒達には「福音を宣べさせ」た。真実な福音を語ってこそ偽りを追い出せるというものだ。これは悪霊の追い出しを否定するのではなく、あくまでも霊的な側面での話であるが。
とにかく主は退いた。肉的な勝利を取る王ではない。だからパリサイ人達を返り討ちにせず、病人達を拒まず…これがイザヤの預言(傷んだ葦を折らず、くすぶる燈心を消さず)の成就である。最後に、ユダに裏切られる(19)。それで完全に地上から退く事となる。それも福音(救いの計画)の完成の為だ。それが真の王としての主の姿である。
2026年1月25日礼拝メッセージ マルコ2:23~3:6 「人間のため」 ![]() メッセージは11分45秒からです。
メッセージは11分45秒からです。
律法は、隣人の畑の穂を手で摘む事は許可している(申23:25)。だがそれを見たパリサイ人達は怒った。それが安息日だったからだ(23~24)。穂を摘む事を刈り入れ(労働)だと解釈したのである。勿論、主はそれを罪だなどと思ってはいない(25~26)。すると主は、法・秩序の破壊者なのか。いや、平和の君だ。では何故、主は安息日にも働いたのか。それは「父は今に至るまで働いている」(ヨハネ5:17)からだ。
定説では「神は7日目に休んで、それを聖とされたのだから7日目は安息日、働いてはならない」という事になっている。だが、それは間違いだ。神は休んでいない(と主は言われた)のである。
確かに律法には、安息日には働くなとあるが、その発端はマナだ。それは土曜日には降らない(金曜に2日分降るから)と神は言うのに、従わず、あくせくする人々がいたので、民に神への信頼を学ばせる為に土曜日(7日目)は働くなと命じたのである。なのに、それが形骸化して、単なる無意味な規則に成り下がってしまっているだけなのだ。
続いて、すぐに主は手の萎えた人を癒したが、癒す事が目的なのではない。「安息日に働いて何が悪いのか」と主張する為だ。問い掛けられているのは「安息日にしていいのは殺す事か、生かす事か」なのである。それを、癒しに注目し過ぎて見失ってはいけない。
律法は、人を縛る為ではなく、キリストに導く為のものだ。その為に使うなら、律法は聖く、良いものだとパウロも言う。つまり、人を縛る為に律法を使うのは、悪なのだ。律法によって人が苦しむなら、律法は悪魔の道具となってしまっているという事だ。
安息日(に限らず、律法全て)は、人間をキリストに導く為のものだ(27)。だから、安息日に働かない事より何より、一番重要なのは、キリストを主とする事である。キリスト無くして命は無い。そのキリストを差し置いて、律法が優先されるなら本末転倒だ。全ての権威は主にある(28)。それでも、イエスを葬り去ろうとした(主に逆らう)人達は(3:6)、やがて主によって自らの魂が滅ぼされる事に気付いていない。主は安息日にも、終わりの時にも、主だ。私達は、神の国に至るまでずっと、イエス様を主とする者でありたい。
2026年1月18日礼拝メッセージ マルコ2:18~22 「必要なら」 ![]() メッセージは11分半頃からです。
メッセージは11分半頃からです。
主の弟子達は何故、断食しないのか、と問う人々に「花婿が一緒にいるから」と答えた主(18~19)。つまり、キリストが共にいる間は断食出来ないという事だ。何故なら、断食は悲しみの表現だからである。救い主が来た(喜びの)時に、何故、悲しむ事が出来ようか、という事だ。その点、律法学者・パリサイ人達の断食は、うわべだけで何も悲しんでなどいない。ただ宗教的熱心さを誇示する為のものだった。だから主は、断食する時には人に分かるようにするなと言われた。もっとも、主は断食そのものを否定している訳ではない。必要な時にはする、と言うのである(20)。実際、その通りに、弟子達は主の昇天のあと断食して祈った(使徒1:14)。
所で、聖書の中に「断食せよ」という教えはあるのか。「断食する時は、こうしなさい」と主は言われたが「日常的・定期的に断食せよ」という教えは無い。主が言われたのは「必要な時にはする」という事だ。ゆえに、必要と感じた人々が「断食していた」事を聖書は記しているに過ぎない。だから、必要を感じないのに断食するのは、パリサイ人達と同じく、宗教的熱心さを誇示する為なのかもしれない。
さて、その断食について説明する為に、布切れと皮袋の話になる(21~22)。まず「古い着物・古い皮袋」は「律法主義」の事だ。そして「新しい布・新しいぶどう酒」は「福音(イエスは救い主)」だ、という事は分かる。その福音は律法主義では受け取れない。「イエスは主」という福音は、聖霊(新しい皮袋)によって受け取るのだ。
そこで、断食との関わりだが…断食自体は悪くない。だが、信仰熱心を誇示する為(見せかけ)の断食は意味が無い。悲しみを表現するなら、心からの悔い改めがあってこそだ。つまり、見栄の断食で福音の恵みは受け取れない、聖霊(新しい皮袋)による心からの悔い改めこそが福音の受け皿だ、という事なのだ。
だから、事ある毎に「新しい皮袋になろう」とする必要は無い。「新しいぶどう酒」は「流行の教え」の事ではないのだ。本当に必要なのは、真実な信仰の悔い改め=信仰がどこに向かっているのか…それが間違っていたなら方向転換する事である。
2026年1月11日礼拝メッセージ マルコ2:13~17 「向かう方向」 ![]() メッセージは11分40秒からです。
メッセージは11分40秒からです。
レビ(マタイ)が「ついて来い」と主に言われて、すぐに従ったのは何故か。アンデレ達の場合は必然的な伏線があったが、レビには無い。それでも彼はすぐに主について行った。やはり「単純に従う信仰」なのか。しかし、ついて行った先は、自分の家だった。つまり、ここでの主の「ついて来い」は「お前の家に行くぞ」という事なのだ。何しろ、そこで大勢の人達と食事をするつもりだったのだから、家主に来てもらう必要はあるし、取税人で悪どく儲けていたレビの家はうってつけだったのだ。その後、レビは主の弟子となるが、それは自由だ。
とにかく、レビの場合は、いわゆる「召命」とは少し違う様だ。ただ目的は、レビの家で罪人達と食事をする事である。理由は「罪人を招く為に来た」からだ(16~17)。そして「招く」とは、献身へ…ではなく、天国へである。レビも、その罪人の一人として招かれたから弟子となったのである。だが、そんなレビ(マタイ)を主は選んで、福音書を書く器として用いたのだ。
では何故、選ばれたのか。それは罪人だからだ。すると選ばれなかった人は、正しい(罪の無い)人だったのか。いや、そんな人はいない。しかし「自分は正しい。罪が無い」と思っている人はいる。主は、そんな人は天国に招かない、とは言わない。「天国への招き」は全ての人にだ(ヨハネ3:16)。ただ「自分には罪は無い」と言う(罪を認めて赦しを得ない)人を「天国に招き入れ」はしない。「天国に招く」のと「天国に招き入れる」のは別問題だ。そこで大事なのは、赦されたか、赦されていないか、である。悔い改める(方向転換する)なら赦される、それが福音だ。たとえクリスチャンでも、信仰の向かう方向によっては悔い改め(方向転換)が必要である。その思いの向かう方向が地上の事だけなら、最後は滅びだと聖書は言う(ピリピ3:19)。勿論、地上の事は大事だ。無視する訳にはいかない。しかし、天にも心を向けなければいけない。その為には、天にこそ大いなる宝がある事を知る必要がある。宝のある所に心は向かうからだ。
私達は、天にどれ程の宝があるのかを聖書を通して知る…その様な方向に歩み続けよう。
2026年1月4日礼拝メッセージ マルコ2:1~12 「主よ、見て下さい」 ![]() メッセージは13分半過ぎ頃からです。
メッセージは13分半過ぎ頃からです。
当時、人々は「病は罪があるから」と考えていた。逆に言えば、病が治ったのは罪が消えたからだという事になる。おかしな考えである。だが主は、それを逆手に取って中風の人を癒した。つまり「彼が癒されたのは罪が赦された証拠だ。口先だけではない」という訳である。
問題は、何故、中風の人は罪が赦されたのかである。主は「彼らの信仰を見て」(5)とあるが、どれが信仰なのか。他人の家の屋根をはがした事? 床を吊り下ろした事? 確かに、癒しを求める強い心はある。立派な友情もある。しかし、それらが「罪が赦される為の悔い改め」なのだろうか。彼が悔い改めたという事実はどこにあるのか。見つからない。私達人間の目には。しかし主は「見た」(5)のだ。
主は、人の心を見抜くお方である(8)。ヨハネ1章では、その場にいなかったナタナエルの行動をも「見た」し「本物のイスラエルだ」と、彼の内面をも見抜いた。まさに、神は心を見るのである。それが全知なる神というものだ。だから、きっと、中風の人と友人達は、主のもとに来る前に悔い改めていたのだろう。それを主は「見て」見抜いたのだ。だから、ルカによれば「あなたの罪は赦されました」(5)という部分は、過去完了形で書かれている。つまり「過去において赦されたし、今も赦しは継続している」という事だ。
大前提として罪は「悔い改めたならば赦される」のである。ただ、真実な悔い改めかどうかは、表面では分からない。だから神は心を見る。ゆえに、たとえ教会に行った事が無くとも、心を見る神が「この人には信仰がある」と認めて下さる場合もあるという事だ。だから、異端的なセカンドチャンス論など無用なのである。これは福音だ。
神は、色々な方法で語る(ヘブル1:1~2)。被造物を通しても(ローマ1:20、詩篇19:1)。その時に神を受け入れるなら、その人は神に向かう(方向転換した)という事であり、それが悔い改め(メタノイア)なのだ。その心の中を神は見る。そして赦しを与える。この中風の人の様に。
決して、他人の家の屋根をはがすのが信仰なのではない。悔い改め…それを主は見て、赦しを与えたのだ。私達も主に、心の中の信仰を見て頂ける様にしたいものである。
2026年1月1日元日礼拝 Ⅰテサロニケ5:1~11 「元日から」 ![]() メッセージは11分からです。
メッセージは11分からです。
この日の要約はありません。
2025年12月28日礼拝メッセージ マルコ1:40~45 「福音の妨げ」 ![]() メッセージは14分過ぎからです。
メッセージは14分過ぎからです。
癒しは、根本的には、救い主到来の「しるし」であるが、一方では主の憐みにもよる。主は一人の病人を深く憐れんで癒された(40~42)。だが、その割には彼を厳しく戒めるは何故か。そして、まるで万引きを見逃してやるかの様に追い立てる。腑に落ちない事の最たるは「誰にも何も言うな」と言いながら「人々への証の為に供え物をせよ」という所だ(44)。新共同訳では「人々に証明しなさい」である。「誰にも何も言うな」との言葉に見事に矛盾する。
実は「人々への」は、直訳「彼らへの」だと新改訳の脚注にちゃんと書いてある。「彼ら」とは祭司達の事だ。つまり「聖められた事を祭司達に証明せよ。しかし人々には何も言うな」という事なのだ。これで矛盾は無くなる。なのに何故、あえて直訳を避けて、誤解を招く「人々」にするのか。変な意図が垣間見える。
とにかく、話をまとめると、主が病人を癒したのは、救い主到来のしるし(罪の赦しの象徴としての、らい病の聖め)であり、同時にそこには主の深い憐みもあった。だがそれは、ご利益を求める人々の心の炎に油を注ぐ事になる。だから「何も言うな」と厳しく戒めたが、祭司には、自由を得る為に「聖められた事を証明しろ」という事だ。
所が、彼は言いふらしたので、熱狂した人々で町は溢れ、不本意にも主は宣教も出来ないまま寂しい所にいる事になった。なのに、そこにも癒しを求める人々が詰めかけたので、祈る事さえ出来ない。結論。癒しは福音の妨げになる…けど主は、憐みのゆえに癒してあげたくなる。ジレンマ。愛と義の神にはジレンマがあるのだ。救いたい(愛)けど、裁かなければならない(義)。その二つを両立させたのが十字架であるのに、その福音を妨げては本末転倒だ。
町はずれの寂しい所に一人でいた時の主の心境はいかなるものだっただろう。「救いさえ手に入れば、復活によって完全なる癒し(栄光の体)が与えられるのに、どうして福音を聞こうとしないのだろう」と嘆いておられたのではないかと思う。
終わりの時の近い今、優先すべきは福音だ。それを阻むためにサタンは偽りを吹聴する。私達は、純粋な福音を最優先しよう。
2025年12月21日礼拝メッセージ マルコ1:35~39 「斬新なクリスマス」 ![]() 今回はメッセージのみです。
今回はメッセージのみです。
主は、朝早くから祈っておられた(35)。これは早天祈祷会を教えるものだろうか。いや、一日中人々に囲まれ、一人になれる時間が無かったから、弟子達が寝入った後、暗い内に起きて、一人で祈っていたのだ。それでも、すぐ弟子達は主を追って来た。人々がイエスを捜していたからである(36~37)。
では人々は、朝早くから何を求めて主を捜し回ったのか。それは癒し・奇跡を求めてだという事は32~33節からの文脈で分かる。所が主はそれを無視する。「行って直してあげよう」とは言わず、背中を向ける様に「向こうの村へ行こう」と言うのである(37~38)。何故か。
ポイントは、キリストは何の為にこの世に来たのかという事だ。悪霊を滅ぼす為ではないし、病を癒す為でもない。それらは救い主到来の「しるし」であって、しるしは目的ではない。目的は、福音を宣べ伝える為(そして十字架で…)だ。「その為に出て来たのだから」病の癒しばかりに時間を費やしていないで「近くの別の村里へ行こう」という訳なのである。
さて、キリストは、どこから出て来たのか。ナザレか。いや、ナザレの前には別の所に居た。ベツレヘムか。いや、そこは産まれただけで「居た」とは言えない。それ以前に、そもそも「始めから居た所」がある。神の御座・天だ。そこから「出て来た」のである。神の在り方を捨てる事が出来ないとは考えないで、王なのに馬小屋の飼い葉桶に赤子として産まれる為に…。何故、そこまでして出て来たのか。人間に救いの道を示す為だ。それがクリスマスなのである。だから「救い主が産まれた」と言うよりも、主は自分の意志で「出て来た」のだ。
こうして主は、福音を告げ知らせると共に、悪霊も追い出した(39)。悪霊の追い出しは、神の支配の一部分であるが、やがて完全な神の支配が成される時が来る。天国だ。キリストを信じるなら天国に入れる…それが福音であり、それを知らせる為にキリストは出て来た、それがクリスマス。だから天国に入らなければクリスマスが無駄になってしまう。気分だけ、飾り付けやイベントだけ…それはクリスマスの無駄使いだ。何の為にキリストは来たのかを、しっかり覚え続けよう。
2025年12月14日礼拝メッセージ マルコ1:16~34 ![]() メッセージは12分過ぎからです。
メッセージは12分過ぎからです。
既にバプテスマのヨハネの弟子となってはいたが、ヨハネが捕えられたので仕方なく漁に戻っていたアンデレ達。そこへ「神の小羊」とヨハネが言ったイエスが現れ「ついて来い」と言う。再び神の道を歩める、渡りに船だとばかりに、すぐに全てを捨ててついて行ったのだ。
さて、律法学者の口先だけの教えしか聞いた事が無かった人々は、イエスの権威ある教えに驚いた(21~22)。しかし問題は、そのイエスをどう認識するかだ。悪霊はイエスに「私達を滅ぼしに来た」と言う(23~24)が、これはミスリードである。キリストは福音を宣べ伝える(十字架で救いの道を開く)為に来たのだ。悪霊を滅ぼす為だけなら何も地上に来なくても出来る、それが全能の神だ。しかし、罪の無い人として身代わりに十字架で死ぬ為には、地上に来るしかない。その十字架・福音から人間を遠ざける為に悪霊はわざと言うのである。だから主は「黙れ!」と言って悪霊を追い出した(25~26)。その結果「イエスは悪霊を追い出す」という評判が広まってしまった(27~28)が、サタンもさるもの、キリストの妨害をやってのけたのである。
キリスト教でなくとも、他の宗教にも奇跡・癒しが起こる事がある。だが、罪の赦し・永遠の命・天国は聖書にしか無い。だからこそサタンは、人間を十字架から遠ざけたい(奇跡・癒しに目を向けさせたい)のだ。そんなサタンの思惑が見て取れる出来事であり、悪霊追い出しも手放しでは喜べない。ただ、シモンのしゅうとめの熱病が癒されたのは心温まるエピソードだ(29~31)。しかし人々はひたすら癒しを求めて殺到する。主も憐みのゆえに癒す(32~34)。そこでも主は、悪霊がものを言うのを許さなかった。それは「悪霊共がイエス(が十字架で救いの道を開くという事)を良く知っていたから」である。そこから人々の目を逸らさせる為の悪霊の発言を封じたのだ。
だから、キリストは悪霊を追い出すお方だと思うべきではない。キリストは悪霊を滅ぼすお方なのだ(ただし、最後にはだが)。それまでは、毒麦と同じ様に、ある程度放置なのである。それが現状だという認識を持たなければ悪霊追い出しに振り回されてしまう。私達は、正しい認識を持って、真理を掴んで、主について行こう。
2025年12月7日礼拝メッセージ マルコ1:9~15 ![]() メッセージは11分半からです。
メッセージは11分半からです。
マルコは、福音とは何かという事に焦点を絞って福音書を書いた。ゆえにストーリーとしてはカットされている部分が多く、要点のみを記している。つまり「キリストの宣教の要点は何か」という事がマルコの伝えたい事なのである。要点、それが14~15節だ。
しかし「福音を信じなさい」と言われても、その時点においては十字架も復活も未だ成就していない。では、主が「信じなさい」と言う福音とは何か。具体的には…まず、主はイスラエルに宣教したのだから、その福音は、イスラエルにとっての良い知らせである。ただ、イスラエルの民が、それを良い知らせだと思うかどうかは別だが、主はイスラエルに対して「これがお前達への良い知らせだ」と言う。その良い知らせ、それが「時が満ち、神の国は近くなった」なのである。つまり、イスラエルへの神の約束(神の国)が成る時が来た、という事だ。それがイスラエルへの福音なのである。所がイスラエルは、神の国とはイスラエル王国の再建だと考えていたので、主の宣言は彼らにとっては良い知らせではなかったのである。要は、神の国とは何なのかという事を分かっていないという事だ。
神が約束した「神の国」とは「神の支配」である。それが近付いたという事は、それまでは、神が支配していなかったという事だ。すなわち、イスラエルは神のものになっていなかった(神の支配を拒んでいた)のである。それを「悔い改めなさい」と言うのである。言い換えれば「福音を信じなさい」=「神の支配を受け入れなさい」という事だ。あくまでも神の支配を拒むなら滅びだからである。それはイスラエルに限らず、全ての人に当てはまる。だから、神の国・神の支配とは結局、全ての人にとっても「福音」なのだと言える。それは救いであり、希望であり、慰めである。受け入れて何の損も無い。
ただ、2000年前に主が現わされた神の支配は、悪霊の追い出しや病の癒し等、限定的だった。しかしやがて神の支配が完成する時が来る。その時までに悔い改める事が必要だ。「完全になれ。聖い人になれ。主の似姿になれ」などという「行いの義を追及する信仰」あるいは律法主義、ご利益信仰…を悔い改めるべきなのである。
2025年11月30日礼拝メッセージ マルコ1:5~8 ![]() メッセージは11分頃からです。
メッセージは11分頃からです。
逐語霊感説に従うなら、「全住民が罪を告白し洗礼を受けた」(5)のだから、一人残らず救われたという事になるはずである。だが事実は、多くの人がヨハネから洗礼を受けた止まりであって、それだけでは救われない。たとえ、その時、罪を告白していてもだ。
そもそも、どんな罪を告白したのかである。律法違反か。いや、ヨハネが求めた悔い改めは、そんな律法主義や形骸化した信仰から離れる事であり、それこそが主の道備えなのだ。結局、大多数の人は「ヨハネのバプテスマとは何なのか」という事が分かっていないのである。そして今、信仰の本質さえも見失われているのかもしれない。
さて、ヨハネの風貌(6)は、砂漠の住人特有のものだが、否が応でもエリヤを思わせる。むしろ、それが目的かもしれない。そして彼は言った。「私より力のある方が、あとから来る」と(7)。という事は、ヨハネにも少しは力があったという事になるが、彼は何か奇跡を行ったのだろうか。いや、あるとすれば「言葉の力」だ。キリストによる救いへと導く為の悔い改めを説いた…それが彼の力である。しかし、あとから来られるキリストは「人を救う(命の)言葉」を持っている。だからヨハネは「自分にはキリストの靴紐を解く値打も無い」と言った。「靴紐を解く」のは奴隷の仕事であるから、ヨハネは「自分は奴隷以下だ」と言ったのである。更に、力の差はバプテスマにおいてもであると言う(8)。「キリストは、あなたに聖い霊を浸す」という事だ。それは、エゼキエル36:26~27の預言の成就であり、イエスが救い主であるという事のしるしなのである。
そういう訳でヨハネは紛れもなく再来のエリヤであり、主の道備えをする為に遣わされた偉大な預言者だ。しかし救い主キリストは格段に格上だ。だから、ヨハネが偉大であればある程、キリストの偉大さが引き立つのである。その偉大なヨハネでさえ奴隷以下なら私達は何者かと思うが、そんな小さな者を救う為に主は自らの命を犠牲にされた。そんな王は他にいない。そのキリストを、自らの利得の手段にするなど有り得ない。信仰の本質を分かっていないという事だと言わざるを得ない。私達はキリストの偉大さを知って、そのしもべであろう。
2025年11月23日礼拝メッセージ マルコ1:2~4 ![]() メッセージは11分40秒からです。
メッセージは11分40秒からです。
バプテスマのヨハネは、神の計画によって主の道を整える為に遣わされた。果たして、主の道は整った(真っ直ぐになって、主は苦も無く・拒否や反抗等される事なく歩めた)のか。いや、主は拒まれた。ではヨハネは使命を果たせなかった(神の計画は失敗した)のか。
ポイントは、ヨハネの使命(主の道を整える)とは、どういう事なのかである。それは、聖書全体が示す神の計画(2~3)の通りに、罪が赦される為の悔い改めのバプテスマを説く(4)事である。ただ注意すべきは、ヨハネのバプテスマを受ければ罪が赦されるのではないという事だ。罪が赦されるのは、真の悔い改めによるのであって、そこに導く為のヨハネのバプテスマなのである。だからヨハネは「悔い改めよ」と叫んだ。それが聖書全体の示す神の計画だから、その通りに。
では、悔い改めるべき罪(的外れ)とは何か。ユダヤ人は皆、聖書の神を知っている。それでも何の的が外れているのか。それは、信仰の的だ。例えば律法主義、あるいは形骸化した信仰…それらを悔い改めて福音(キリスト)を信じるべきなのである(使徒19:4)。それを説くのが「悔い改めのバプテスマ」であって、その為に遣わされたヨハネの、その使命は果たされたのである。だから、ヨハネのバプテスマを受けた人は、キリストの元に行き、キリストを信じ受け入れなければならない。それが「悔い改め」であって、そうすれば救われるのだ。その様に、主の道は整えられた。だが、人々は悔い改めなかったのだ。
改めて、救いの条件は、善い人や完全な人やキリストの似姿になる事ではない。悔い改める事だ。それが聖書全体が示す神の計画である。所が「いいや、それだけではダメだ」と思わせる、それがサタンの策略だ。もっと祈らなければ神に見捨てられる…、もっと成長しなければ…、もっと、もっと…でないと神に喜ばれない…と思うなら、まんまと惑わされているという事である。クリスチャンは、悔い改めてキリストを信じた時点で神に喜ばれているのだ(ルカ15:7)。ただし、そのあと、信仰が曲がってしまったら神に喜ばれはしないが。
だから、純粋な信仰(悔い改める事が、聖書全体の示す神の計画だという事)を保つ事が必要なのである。そうすれば救われる。
2025年11月16日礼拝メッセージ マルコ1:1 ![]() メッセージは11分半頃からです。
メッセージは11分半頃からです。
マタイの福音書はユダヤ人向けに書かれ、マルコはローマ人向けに…等と言われているが、その様な分類とは違う面がマルコにはある。それは、マタイやルカはキリストの生涯(系図、誕生物語、幼少の頃のイエス…)を描いている(伝記的である)のに対し、マルコは「キリストの福音」に特化した書である(福音とは何か…を、キリストの言動を通して示そうとしている)という事だ。
福音、それはパウロが示している通りであり(Ⅰコリント15章)、他に福音は無いと聖書は言う。しかしマルコは十字架と復活しか書いていない訳ではない。思うに、マルコは「生きる力としての福音」を描こうとしているのだろう。つまり、まず十字架と復活は「永遠の命を生きる為の力」であって、欠かす事の出来ない「キリストの福音」だ。では、地上で生きる力は福音には無いのか。それをキリストは与えてくれないのかと言えばそうではない。「地上で生きる力」それも「福音」なのである。勿論、それも「十字架と復活」があってこそのものだ。それ抜きで「地上で生きる力」と言えば、やはりお金という事になってしまう。あくまでも信仰に基づく「生きる力」でなければならない。
そこで「地上で生きる力」だが、たとえ財産や名誉があっても、希望が無ければ人は生きて行けない。その希望を失わせようとするのは誰か。サタンである。その手口は、偶像、無神論、口伝律法等、常に偽りによってである。ゆえに、そういうものから解放される事(偽りからの解放)が生きる力・希望となるのであって、それが「福音」なのである。すなわち、真理を知る事によって偽りから解放され自由になるという事だ。では、真理とは何か。それは、キリスト御自身だ。主は言われた。「私が真理だ」と。だから、キリスト御自身が「福音」だと言って過言ではないのである。キリストは、信じる者に永遠の命と共に、地上で生きる力も与えてくれる。逆に言えば、キリスト無しでは永遠の命も地上の命も無いのだ。
キリストによって今、私達は命が支えられている。そして、キリストの十字架と復活のゆえに永遠の命が約束されている。それらが福音なのだ。この福音を受け取って力強く生きる者となろう。
2025年11月9日礼拝メッセージ マタイ28:18~20 ![]() メッセージは12分頃からです。
メッセージは12分頃からです。
大宣教命令と呼ばれる個所だが、そもそも宣教とは何か。未信者に伝道する事か。いや、宣言し(宣言を)教える事であるがゆえ、信徒に教える事…それも宣教なのである。
そこで「主の命じた全ての事を守る様に教えよ」だが、全てを守らなければ失格・地獄と言うなら、それは律法主義だ。しかし「神を愛し隣人を愛する」事によって、全ての事を守る…が可能となる(マタイ22:37~40)。ただし「隣人を愛する」とは、救霊の思いと行動の事(それが神の愛)なのであって、親切にしたり仲良くする事とは違う…という様な事を教えなければならないのである。
次に「あらゆる国の人々を弟子とせよ」だが、誤解してはいけない。これは「全ての人をクリスチャンに…」ではなく「これからは異邦人にも伝道せよ」という事だ。
続いての命令だが「父・子・聖霊の御名によってバプテスマを…」なのか「イエス・キリストの御名によって…」なのかという論争がある。だが、それは本題から外れた事だ。実はこれは「神の御名の中に浸せ」という命令なのである。と言うのは「によって」は、ギリシャ語の「エイス(~の中に)」となっているからである。もし「誰の名前によってなのか」と言いたい時は「エン」でなければならないからだ。要するに主は「洗礼を受けて弟子となった人を、更に神様漬けにせよ」と命じられたのだ。決して洗礼式の事ではない。勿論、洗礼式は必要だが、この命令は更にその上を行く。「弟子達を神の御名の中に漬け込め」…それが大宣教命令なのである。一夜漬けでは神の御心が染み込まないからだ。キリストに似た者になるなど程遠い。
この大宣教命令が下された理由・根拠は「主には一切の権威が与えられている」からだ。つまり、救いも裁きも、主に権威があるからなのである。その権威ある主は「いつも、あなた方と共にいる」と言われた。「あなた方」とは誰か。全ての人ではない。主の命令を守る人の事だ。では主の命令とは何か。どの命令を守ればいいのか…それを教えろと主は言われているのである。主がその人と共にいる為だ。
私達は、主が共にいて下さる者でありたい。
2025年11月2日礼拝メッセージ マタイ28:7~17 ![]() メッセージは12分からです。
メッセージは12分からです。
恐れるマリヤ達に、天使は「復活の主とガリラヤで会えると弟子達に伝えよ」と語った。それを受けて急ぐマリヤ達に現れた主が同じ事を繰り返して言う。それ程重要な事なのだ。そして「恐れるな」も繰り返された。恐れると正しい判断・行動が出来ないからだ。つまり、何としても復活を伝えてもらいたいのである。
一方、番兵達が一切の出来事を祭司長の所に報告に来た。通常なら指揮官である総督ピラトに報告すべきだが、任務失敗に伴う刑罰・死刑を恐れて、回避する為に泣きついて来たのだろう。それで祭司長達は番兵に指示を与えて庇ってやるのだが、そんな義理は無いはずだ。しかし思惑がある。すなわち、両者共、キリストの復活を隠したいという事だ。それがどれ程の恩恵を自分達にもたらすか…その点において利害が一致しているのである。その結果、イエスの遺体は盗まれた(復活したのではない)という話が広く広まってしまった。利得の為なら真実はどうでもいい事とされる。それは、どの世界でも同じだ。
そんな中で弟子達は、主に会う為にガリラヤに行った。騙されなかったのだ。自分達は盗んでいない事(真実)を知っているからだ。その様に正しい行動をとる為に「恐れるな」「ガリラヤに行け」を2回言われたのである。それで弟子達は見事に主とお会いした。「しかし、ある者は疑った」とあるが、トマスの事だろうか。彼は主の手に釘の跡があれば「甦った」と信じると言った。しかし、それなら単なる生き返りに過ぎない。結局トマスは復活を分かっていないのだ。復活の主は栄光の体である。だから「(傷跡を)見ないで信じる者は幸い」と主は言われたのであるが、これも甚だしく誤解されている。「自分の願い事がまだ実現していなくても、見ないで信じよう」という風に。
とにかく、広く広まっている話には気を付けたい。典型的なのが進化論である。現に、大多数の人々がそれに騙されている。そして、大本営発表とも言うべきテレビ・新聞等、マスコミによる過度の煽りだ。
真実はどこにあるのか。勿論、少数意見なら正しいという訳ではないが、こと天国への道については主の言葉の中に真実があるのは間違いが無い。全力でそれを読み解き、真実を知る者となろう。
2025年10月26日礼拝メッセージ マタイ27:62~28:6 ![]() メッセージは12分半頃からです。
メッセージは12分半頃からです。
安息日であるにも拘らず、禁を破って自ら異邦人(ピラト)に接触した祭司長達の目的は、イエスの墓の番をしてもらう事だ。弟子達は主の遺体を盗む度胸などもはや失っていたのにである。しかし、この処置が結果的に主の復活の(盗まれたのではない)証拠となった。
さて、復活の朝、番兵達は天使を見て、非常なショックを受けた。それは任務失敗に伴う刑罰(死刑…十字架)を恐れる余りの事だろう。だが問題は、天使は何の為に来たのかだ。主を墓から出して差し上げる為ではない。復活の主は壁をもすり抜ける栄光の体だ。天使は、マリヤ達に空の墓を見せる(主は復活したと教える)為に来たのである。何故なら、その時点ではまだ誰も復活を信じていないからだ。復活は聖書の預言であり、主御自身も何度も前もって語られたのにである。
弟子達だけに限らず、人間は、自分が信じられる範囲でしか信じない傾向がある。それだけならまだしも、厄介なのは、自分が信じたい事しか信じないという事だ。たとえ真実に対してでも、それが自分の望む事でないなら目をつぶる。しかし、私達は信じるべきだ。自分の願いではなく、神の言葉・神の約束を(ルカ16:27~31)。あえて言えば、聖書を丸ごと信じるのではない。聖書には、愚かな人間の間違った言葉も沢山あるからだ。例えばヨブ記。だから信じるべきは、聖書に込められた「神のメッセージ」である。そして「それ」が何であるかを知る為に聖書を調べるのだ。つまり、聖書の文字面を鵜呑みにしてはいけないという事である。何故なら、聖書そのものが永遠の命なのではなく、聖書の中に永遠の命への道があるのだからだ(ヨハネ5:39)。
そういう訳で聖書は、じっくり読み込んで調べる必要がある。聖書が証言しているのは何なのか、を。そして悟ったら、それを信じるのである。パウロも、よく考えてから信じるべきである事を言っている(Ⅰコリント15:2)。勿論、まずキリストを信じるのが先決で、そのあと聖書をじっくり学ぶ・調べる・考える…が通常だが。最悪は、聖書を悟らないまま自分の信じたい事を信じ続ける事だ。それが、いびつなキリスト教を作り出す一因である。私達はキリストの真の弟子となる為に、留まるべき御言葉は何かを探し求め続けよう。
2025年10月19日礼拝メッセージ マタイ27:55~61 ![]() メッセージは14分頃からです。
メッセージは14分頃からです。
主の死を遠くから眺めている女性達が沢山いた。その内の何人かの名前がマリヤであった。「そこに重大な意味がある」と、ある人は言うが、むしろ「遠くから眺めていた」という事の方が意味深い。
午後3時に主の死。あと3時間程で安息日。それまでに葬らなければならないが、通常は、犯罪人の死体は、それ専用の穴に投げ入れられて獣や鳥の餌にしてしまう。女性達にはそれを阻む力が無く、ただ遠くから眺めるしかなかったのだろう。そこに突如現れたのがアリマタヤのヨセフだ。有力な議員で、主の弟子となっていたが、ユダヤ人を恐れて信仰を隠していた。なのに恐れを振り払って、主の体の下げ渡しをピラトに願い出た。神が彼の心を動かし、用いたのだ。何しろ、議員としての力があり、金持ちで、近くに新しい墓を持っていた。これ程の好条件を備えた人物は他にはいないのだから。そして、議員仲間で同じく隠れ信者のニコデモも加わった。全て備えられていたのだ。
一方、一番偉いのは誰か…等と息巻いていた使徒達は殆どが逃走(尤も、彼らも後には聖霊の力によって勇ましく主の証人となるのだが)。逆に、逃げずに残った隠れ信者達が主の葬りの為に大きく用いられた。そして弱い女性達も。彼女達は主の葬られる所をしっかりと見ていた。何故なら、時間の無い中での応急的な葬りだったので、安息日が明けたら油を塗りに来ようと思っていたからだ(マルコ16:1)。主を案じて「遠くから眺めていた」がゆえに、葬りの現場にも立ち会う事が出来たのだ。彼女達と隠れ信者達のおかげで主は、犯罪人としてではなく(鳥の餌になる事も無く)王として葬られたのである。
結局、神にどの様に用いられるかは決して均一ではないという事だ。だから、私達は主のしもべとして(力があろうと無かろうと)自分に出来る事(自分だから出来る事)を以て忠実に仕えたい。それは、派手な人に褒められる様な事でなくても構わない。マルタの妹マリヤの様に主の側で御言葉に聞き入るだけでもいい。主はそれを「どうしても必要な事」と言われた。そう、主の下に留まる事こそ、どうしても必要な事なのである。怯え、恐れ、失望して去って行くより、何も出来なくても主の為に、主の側にいる方が尊い。それが主の栄光となる。
2025年10月12日礼拝メッセージ マタイ27:54 ![]() メッセージは12分頃からです。
メッセージは12分頃からです。
「百人隊長の信仰告白」とされるが、疑問がある。まずマタイは、主語を複数形にしている。百人隊長だけでなく、共にいた兵士達が皆、信仰を持ったのか。そして、仮に隊長だけだとしても、彼は「イエスは私の救い主」と信じたのか、すなわち、救われたのかという事だ。
救われる為の絶対条件は、悔い改めだが、「この方はまことに神の子であった」という言葉は、その条件を満たしているだろうか。彼がそう思った理由は、地震や色々の出来事を見て恐れたからだと聖書は言うが、奇跡を見たからとて必ずしも信じる訳ではないというのは祭司長達の行動から明らかだ。一方、マルコでは、その死に様を見たから…となっている。百人隊長は仕事柄、うんざりする程の十字架刑(凄惨な死に様)を見て来たであろう。だからこそ「この男は違う、こんな事は有り得ない、普通の人とは思えない、まさに神の子だ」と感じたのではないか。異邦人の感覚としては「凄い人=神」であるのは事実だ。特に「イエスは神の子を名乗った」と言って訴えられているのだし、死ぬ間際に「父よ、我が霊を御手に委ねます」と言えるなんて人間は、そうはいない。それを間近で見ていたからこそ百人隊長は「この男の『神への信頼』は凄い、神の子と言って過言ではない」と称賛したのではないか。だが、それを信仰と言えるか、である。
結局、彼は救われた、と断言する事は出来ないと思う。人間は表面的な部分で判断するが、救われる為に問われるのは、心の中の信仰が真実であるかどうかだ。しかし、それはうわべでは分からない。人の心の中(真実な信仰を持っているかどうか)は神だけが知るのだ。
要は「イエスをどう評価するか」ではなく、「イエスを主とするか」が問題なのだ。「イエスは神の子・救い主」と認めていても、イエスを主として従っていない(イエスをしもべの様に扱い、好き勝手な注文をする)なら、それは信仰とは言えないだろう。正しい在り方は「イエスが主で、自分はしもべ」である。つまり、主が何でもしてくれるのではなく、自分が主の為に何でもするという事だ。ただし「主が『やれ』と言われた」と、好き勝手な事をするのは頂けないが。だから「主は本当は何を言われたのか」を知る事が必要なのである。
2025年10月5日礼拝メッセージ マタイ27:51~53 ![]() メッセージは13分半頃からです。
メッセージは13分半頃からです。
至聖所を仕切っていたぶ厚い(その厚みは20センチという)幕は、神と人との隔たり(罪)の大きさの表れであるが、それがキリストの死によって裂かれた事によって、誰でも神との親しい交わりに入る事が許され、祭司として賛美や祈りが出来る様になった。恵みである。
他にも、キリストの死の際、地震が起き、聖徒達の体が生き返った。それも「多くの」であるから大事件だ。その割にアッサリしている。これ以降聖書はその件について何も語らない。ちなみに、その出来事はエゼキエル37:12の預言の成就だと言われるが、ならば何らかの意味があるはずだ。では、この「生き返り」をどう受け取るべきなのか。
第一に、その時点ではキリストは未だ復活していないのだから、生き返った聖徒達は、栄光の体にはなっていないという事だ。何故なら、栄光の体に復活する「初穂」はキリストと決まっているからである。すなわち、聖徒達は単純に体が生き返ったという事だ。ラザロの様に。
では何の為に生き返ったのか。同時に起きた地震(神の怒り)等の意味は何か。驚くべき事に、それらは全て「主の日(裁きと救いの時)」に起こる事の予表なのである。まず暗闇(45)は、アモス5:20の予言通り、主の日に起こる事である。次に、至聖所の幕が裂ける(神の前に出れる様になる)事。それは、主の日には顔と顔を合わせて主を見る様になるという事である(Ⅰコリント13:12)。そして地震・神の怒り・裁きは、黙示録16:17~19にある通りだ。最後に、聖徒達の生き返り。それは、主の日には全ての聖徒達が栄光の体に復活する事である。初穂キリストが復活されたからこそだ。それを示すのが、生き返った人々が「イエスの復活ののちに墓から出て来て」(マタイ27:53)なのである。
この様に、キリストの死の際の出来事は、主の日に起きる事の予表なのである。つまり、やがてその時には、天変地異が起き、神の怒り・裁きがなされるが、聖徒達は栄光の体に変えられて、御国で顔と顔を合わせて主を見るのである。その時、地上での全ての出来事の意味を知る様になる(Ⅰコリント13:12)。それを保証する「しるし」、それがキリストの死の際に現わされているのだ。この壮大な神の救いの御業から漏れる事の無いよう、御言葉に導かれて真っ直ぐ歩もう。
2025年9月28日礼拝メッセージ マタイ27:50 「完成」 ![]() メッセージは13分頃からです。
メッセージは13分頃からです。
ルカによれば、「父よ、我が霊を御手に委ねます」が主の最後の叫びである。それも大声でだから、やはりこれもまた人々に伝える為だ。
主が最後の最後に伝えたかった事は何か。それは当然、信仰である。何しろ主は、信仰の創始者であり完成者だ(ヘブル12:2)。だが、主が来られる前から「信仰」というものは存在していた。聖書の中で一番初めに宗教的行為を行ったのはアベルとカインであろう(創世記4章)。とは言え、彼らが信仰の創始者という訳ではない。全てのものは神によって造られたのだし、人の心に永遠への思いを与えたのも神だ。ただ、創始者(アルケーゴス)という同じ単語が使われている所(ヘブル2:10)では「救いの創始者」とされている。つまり、イエスは「救いに至る信仰の創始者」だという事だ。事実、世の中には様々な宗教の「創始者」がいるが、救いに至る信仰(十字架と復活)を開いたのは主だけなのである。他にはいない。
では、完成者もキリストであるとはどういう事か。十字架と復活は「創始(開始)」である。それを信じて、天国への信仰の歩みが始まるのだ。その信仰の完成型とはどのようなものか。山を動かす信仰か、水の上を歩く事か。いや、信仰の完成…それを示したのが実は、主の最後の叫びなのだ。「父よ、我が霊を御手に委ねます」これこそ、救に至る信仰の完成型だという事は、逆に言えば、これは簡単な様で簡単ではないという事である。つまり、委ねるより足掻いてしまうのだ。強く信じ込む人ほどそうかもしれない。例えば、死期が近付いた時に「きっと癒される、主よー!」という風に。
もし神が「もう帰っておいで」と召して下さるのなら、そんな時は「我が霊を御手に委ねます」でいいのではないか。それこそ、神への完全な信頼だと言える。そして、それこそが「救いに至る信仰」の完成型なのだ。それを主は、十字架の上で見事に成し遂げられた。ゆえに「信仰の完成者」なのである。最後の叫びはそれを教える為だ。
私達は、天国がどんな所か正確には分からない。永遠に生きるのは退屈ではないかとか思うかもしれない。しかし主は、片手片足失っても天国に入る方が良いと言われた。それを信頼してこそ信仰である。
2025年9月21日礼拝メッセージ マタイ27:46~49 「どうして?」 ![]() メッセージは10分20秒頃からです。
メッセージは10分20秒頃からです。
ただでさえ死にかけているのに、大声で叫ぶには、それなりの理由がある。叫んだのは詩篇22の冒頭の言葉だ。それを聞いて何故だか、ある人達は「エリヤを呼んでいる」と思った。確かに日本人なら「エリ、エリ…」と聞けば「エリヤを…」と思うかもしれない。しかし、それを聞いていたのはユダヤ人だ。「エリ」とは「我が神」という意味だと百も承知の人達なのである。なのに「エリヤを呼んでいる」と思った理由は、思い込みしかない。つまり、人々は「まずエリヤが来るはずだ」と考えていた(マラキ4:5~6)。けど「まだ来ていない」と思っていた。それで「エリ、エリ…」と聞いて「エリヤか?」と連想したのであろう。主が「エリヤは、もう来た」と言われたのに信じないから、思い込みから抜け出せないでいたのだ。
日本人にもヘブル語に詳しい人はいるだろう。しかし、ネイティブのヘブル語話者であるユダヤ人が自国語であるヘブル語の聖書を読んでも、誰がメシアなのかが分からないのである。つまり聖書というものは、ヘブル語・ギリシャ語、英語…を知っていれば分かるという訳ではないという事だ。何故なら、聖書は学問ではないからである。学問的に理解しようとすると、却って信仰から迷い出る。なのに、学問的な権威にすがろうとするするのはいかがなものか。
主の叫びを聞いた別の人は、酸い葡萄酒を主に飲ませようとした。恐らく、黙らせようとしたのだろう。最後の最後で民が惑わされない様にという算段だ。しかし主の叫んだ詩篇22はメシア詩篇である。預言通り救い主は今、十字架についているという事を知らしめる為に叫んだのだ。だが誰も(権威ある宗教指導者達でさえ)理解しなかった。
聖書は、御霊に導かれて悟るものである(Ⅰコリント2:11)。しかし、御霊にではなく肉(この世的なもの・派閥)に属しているクリスチャンがいるとパウロは言う(Ⅰコリント3:1~3)。すなわち、権威・知識・経歴等を信頼の基準にする…それが、肉に属しているという事なのだ。
肉的な考え方を信仰に持ち込んではいけない。私達は、御霊に属する者でありたい。主の叫び「どうして私をお見捨てになったのですか」…「どうして?」…それは、信じる者を救う為である。
2025年9月14日礼拝メッセージ マタイ27:45 「闇の中で」 ![]() メッセージは10分過ぎからです。
メッセージは10分過ぎからです。
主が息を引き取られる直前、全地が3時間暗くなった。春の満月の時期に日蝕は起きないし、日蝕ならせいぜい数分間のもので3時間は有り得ない。だから、特別(異常)な出来事だったのである。
そこで、新改訳聖書2017年版では「闇が全地を覆った」となっていて、ギリシャ語や英語の聖書も「闇が…」となっている。「闇」はギリシャ語で「スコトス」で、宗教的には「神から切断された世界」を意味する。つまり、ただ単に空が暗くなっただけでなく、神の光の無い暗黒が全地を覆った、という事なのだ。神の御子が罪ある人間に殺されるというのはそういう事だろう。真っ黒のドロドロの暗黒に陥ったのだ。だから主は予め言われた。「光ある内に光の中を歩め」と。
すると、主が死んだ(光が消えた)ので、もはや人間には何の希望の光も無いのか。いや、主が甦って今も生きていると信じる者には光がある。それを示す「型」が出エジプト10:22~23だ。約束の地に向かう直前、モーセが天に手を指し伸ばした時、エジプト全土は3日間真暗闇となった――「しかしイスラエル人の住む所には光があった」ここが大事な所である――その「型」通りに主の死の間際に闇が全地を覆った。そして次は、主の日が来る前に暗黒が世界を覆うのである。すなわち、再臨が近付けば近づく程、闇の世になるという事だ。教会も堕落し背教が起こる。それが主の預言(聖書の既定路線)であり、現実である――しかし、キリストの真の弟子には光があるのだ――ヨエルも言っている。主の日が来る前に太陽は闇となるが、主の名を呼ぶ者は救われる、と(ヨエル2:31~32)。ただし、口先で主の名を呼べばいいという訳ではない。必要なのは信仰であるのは言うまでもない。果たして「主の名を呼ぶ者」とは、どんな人か。それは…暗黒の、何の希望も無い恐怖の時、多くの人は叫び、狂乱し、パニックになるだろうけども、そんな切羽詰まった時に、ひたすらに主に信頼して、その名を呼ぶ、それが「主の名を呼ぶ者」なのだ。そんな人が救われる。
平安の時に、主の名を呼ぶのは(賛美するのも)容易い。しかし、闇の中にいる時にも、主に信頼し、主の名を呼ぶ…それが真の信仰者である。私達は、そういう人でありたい。
2025年9月7日礼拝メッセージ マタイ27:37~44 「ののしりか、賛美か」 ![]() メッセージは10分からです。
メッセージは10分からです。
「罪状書き」の原文は「彼の理由」であって、イエスが十字架に付けられたのは「ユダヤ人の王」だからだという事である。罪ではない。だが民衆の願いは、御国ではなく現世御利益であり、強盗達と共に十字架に(それも真ん中に)つけられた姿は民の不信仰を象徴している。
さて、処刑を見物に来た巡礼者達は、頭を振りながら罵って言った。「神殿を壊して3日で建てる人よ」と。遠方からの巡礼者が、夜中にこっそり行われた不当な裁判での偽証の言葉を知ってるのは祭司長達が吹き込んだからだろう。人は権威に弱い。その言葉をすぐに信じる。
最大の問題は、人々が主に「自分を救え」と叫ぶ事だ。人々の言う「救い」とは何なのか。もし主が十字架から降りたら「自分を救った」事になるのだろうか。そしてそれを見たら、民は「凄い! 十字架から降りた! 信じよう!」と言うのだろうか。だとしたら「救い」とは、現世での苦しみ・痛みを取り除く…それが救いだという事になる。事実人々は、そう思っていたのだ。それは「他人を救ったが自分は救えない」という言葉に現れている。つまり、人の病・苦しみは癒したが、自分の苦しみ(十字架)は取り除けない、という事だ。あくまでも、痛み・苦しみからの解放…それが救いだと考えているのである。
しかし聖書の言う「救い」はそれではない。救いとは「地獄に落ちないで天国に入れる」という事である。そして、それは罪ある人間にはどうしても必要なものであるが、罪の無い神の御子には無用だ。キリストは救われる必要が無いのである。だからキリストに向かって「自分を救え」と言うのは甚だ愚かな事であって、滑稽でもある。
「救い」を勘違いしてはいけない。勿論、全能の神は病を癒す事が出来る。問題を解決に導く事も出来るだろう。だが、それらは「憐み」あるいは「恵み」であって、救いではない。だから、たとえクリスチャンが精神的病ゆえに自殺したとしても「救われなかった」等と考えるべきではないのである。もし、病の癒しが救いだと考えるなら、その人の死の時、そこに満ちるのは失望と嘆きでしかない。
キリストが十字架で死ぬという事は、救いの道が開かれるのだから、そこに満ちるのは罵りではなく、賛美であるべきだったのだ。
2025年8月31日礼拝メッセージ マタイ27:24~36 「全ては、完全な…」 ![]() メッセージは12分過ぎからです。
メッセージは12分過ぎからです。
ピラトは、イエスには罪は無いと認めていたのに、十字架へと引き渡した。勿論、そうなる事が御心ではあるのだが、ピラト自身としては正義を行っていないのだから「非がある」と言わざるを得ない。
さて兵士達はイエスを「王に仕立てて愚弄」した。それは珍しい事ではないが、この場合「ユダヤ人の王」に対する当て付けでもある。更に、着物を脱がせて辱め、徹底的にイエスを痛め付けた。一歩一歩、十字架へと確実に近づいて行くが、ゴルゴタへと向かっている時に、クレネ人シモンに代わりに十字架を背負わせたのは、まさかの恩情か。いや、死刑が執行される前に死なれては困るからだ。苦みを混ぜた葡萄酒を飲ませようとしたのも、釘付けしやすくする為(暴れない様に)であって、恩情など一切無い。そして主が、それを舐めただけで飲まなかったのは「十字架の苦しみをまともに受ける為に麻酔を拒んだ」とも考えられるが、「舐めた」のギリシャ語「ギュオマイ」は「味わった」の意である。つまり、これが主にとっての過ぎ越しの食事(新しい契約)の3杯目の葡萄酒となったという事だ。4杯目(契約の完結)は御国での為に残されている。この様に、人間がどう動こうとも、十字架への道・救いの計画は着実に進められて行くのであって、それを教えるのが箴言19:21「人の心には多くの計画がある。しかし主のはかりごとだけが成る」だ。神の救いの計画は完全で、神の約束は絶対なのだから、真実な信仰に留まるなら必ず救われるという事である。
では、真実な信仰とは何か。イエスを信じただけではまだ本当の弟子とは言えない。主の教えの真実にとどまるなら本当の弟子となるのだ。そうすれば真理を知って自由になる(ヨハネ8:31~32)。逆に言えば、真理を知らない=囚われているという事であって、何から自由になるのかと言えば、偽り(サタンの誤魔化し、惑わし)からなのである。
ピラトはイエスを「義人・ユダヤの王」と信じた。だが真理を知らないので自由になれなかった。神の救いの計画は完璧だが、人間の側が駄目ならどうしようもない。勿論、完全な信仰者なんかにはなれない。しかし、真実な信仰者にならなれる。御言葉の表面に留まるのではなく、真実に留まる…それこそ「なすべき正しい事」だ(ヤコブ4:17)。
2025年8月24日礼拝メッセージ マタイ27:11~23 「誤解・曲解・やめたかい」 ![]() メッセージは11分過ぎからです。
メッセージは11分過ぎからです。
バラバは強盗で人殺し・ヤクザの様な人物…という認識が一般的である。しかし民衆は、そのバラバを釈放しろと要求した。祭司長達に誘導されたとはいえ、何故、人殺しの釈放を願う気になったのか。
実は「人殺しをしたのは暴動の時の暴徒達であって、バラバはその暴徒達と一緒に牢に入っていた」とマルコ15:7は言う。バラバが牢に入れられたのは、彼がその暴動を起こした人物だからだ。それも、ローマからの解放を目指す為の政治的な暴動だったのである。だから民衆には人気があった。しかも新共同訳等によれば「バラバ・イエス」という名前になっている(バラバはあだ名でイエスが本名)。それでピラトは「バラバと呼ばれているイエスか、キリストと呼ばれているイエスか、釈放するのはどっちだ」と問うた。民はキリストを選ぶだろうと思ったのだ。何しろ、キリスト・イエスには罪は無いのだから。所が祭司長達が惑わした。「キリストの方は一向にローマをやっつけようとしないけど、バラバの方は釈放されたらまたやってくれる。だからバラバだ」と焚き付けたのだろう。それで民はあっさりバラバを選んだのだ。要は、人々は、キリストの説く「神の国」等よりも、政治的革命者を求めたという事だ。言い換えれば、現世御利益である。しかし、だからと言って、何故キリストを憎むのか、だ。冒涜したからか。いや、それは誤解だ。実に誤解・曲解とは恐ろしいものである。
さてピラトの妻は夢を見て、イエスを「正しい人」と言った。釈放してやってくれ、という事だ。これをどう受け止めるべきか。誰がその夢を見させたのか。神か。いや、キリストを十字架に付けたくないのはサタンである。だから、十字架を否定するペテロに対して主は「下がれサタン」と言われた。つまり、キリストを釈放させる働きはサタンなのである。だから「ピラトの妻は元々主の仲間」とか「神の愛による助け」とかは正しくない。神の愛は十字架で御子を殺す事である。そこに愛が現わされていると聖書は言う。そこを間違えてはいけない。イスラエルは、その曲解のゆえにキリストを憎んだのだから。
幸いなのは、神の言葉を聞いて(ただ聞くだけでなく、御言葉の真意を掴んで)それを守る人達である。
2025年8月17日礼拝メッセージ マタイ27:1~10 「不幸な羊」 ![]() メッセージは11分半頃からです。
メッセージは11分半頃からです。
ユダヤの議会において死刑確定とされた主は、いよいよローマの法律によって裁かれる為にピラトのもとに連れ出された。その時ユダは「罪の無い人の血を売った」と悔やんで首を吊った。とは言え、それは「イエスは罪の無い神の御子」という意味ではない。「イエスは死刑になる様な罪は無い」という事に過ぎない。
因みに、たとえキリストを信じていても自殺したら地獄だという意見がある。それは突き詰めるなら、何の罪も無い完璧な人でなければ天国に入れない(キリストを信じる時の悔い改めは意味が無い)という事になってしまう。一方では逆に、自殺は罪ではないという意見もある。遺族を傷付けない為には「自殺しても地獄ではない」と言いたい…その為には「自殺は罪ではない」という事にしなければならない…という論法だろう。だが、どちらも問題の本質を履き違えている。
信仰から出ていない事はみな罪(ローマ14:23)だが、果たして自殺は信仰から出ている(ゆえに罪ではない)のか。そもそも罪の概念が間違っている。罪とは「的外れ」の事である。では、自殺は的を射ている(正解・当たり)か。いや遺族は悲しむ(生きていてほしかったと思う)のではないか。そう、自殺は的を射ていない。的外れ(罪)なのだ。その的外れ・罪を赦すのがキリストの十字架なのだから、クリスチャンが自殺したからと言って、それで地獄という事にはならない。
さて、ユダが投げ入れた銀貨で祭司長達は陶器師の畑を買った。これが預言の成就だと聖書は言う。端的に言えば、キリストの型としての良い羊飼いゼカリヤをイスラエルは拒んで、賃金として銀30枚を払った。それを神は「私の値段だ(安く見積もられたものだ)陶器師に投げ与えよ」と言った(ゼカリヤ11:12~13)。その通りに、イスラエルの指導者達は、良い羊飼いキリストを拒んだのである。何故なら、彼らは悪い羊飼いだから、彼らにとって良い羊飼いは邪魔なのである。
その様な悪い羊飼いに飼われる羊は不幸だ。羊飼いがいない以上に弱り果ててしまう。だから「羊飼いの声を聞き分けよ」と主は言われた。そして「私の羊は私の声を知っている」と。すなわち、キリストの声(本当の教え)をだ。主の羊とされて主の声を聞き分けよう。
2025年8月10日礼拝メッセージ マタイ26:69~75 「知らない? 知らない!」 ![]() メッセージは12分頃からです。
メッセージは12分頃からです。
ペテロが3度、主を否むシーンである。よく「ペテロもユダ同様、裏切った」と言われるが、実はペテロは、御心・十字架を受け入れられないがゆえに何とかして主を助けようとして(自分まで捕まっては…と思って)しらを切ったのであって、裏切りとは少し違う。
ただ「御心を拒む結果、主を否んだ」のは事実であって、これは一つの型・パターンである。そして、そのパターンを繰り返しているのがイスラエルだ。例えば、出エジプトの後、荒野で(箴言30:9、ホセア13:5~6)。ついには、御心によって来たキリストを拒んで「ナザレのイエスとは何者か」と高ぶって敵対した。御心を拒むがゆえに「イエスなど知らない」と言うのである。だからペテロの件は、単なるおっちょこっちょい的なエピソードなのではなく、言わば預言的な出来事なのである。つまり、やがて来る再臨の時も、ある人々は、それを受け入れられず「キリストなど知らない」と言う事になるのだ。
問題は「主を知らない」と言う人に対して主も「そんな人は知らない」と言うという事である(マタイ10:33)。ペテロは、その主の言葉を聞いていた。そして自身が主を否んだ時(主を知らないと言ってしまったがゆえに)その言葉をも思い出したのではないだろうか。ペテロにしてみれば…本当は主を助けたかった。なのに、主から「あなたを知らない」と言われる…それは悲しかろう。ペテロは激しく泣いた。ペテロは悔い改めたから良かったものの、最悪の場合信仰を失ってしまっていたかもしれない。イスラエルは悔い改めず御心を拒んだままだ。
結局、誰がどれほど否定しようと、主の言葉は全て実現する。御言葉は真実、そして主は真理そのものだ。だから大切なのは、御言葉を悟る事である。たとえ、その御言葉の意味する事が自分の思いと違っていたとしても御言葉・御心を否定してはいけない。御心を拒む…それが、キリストを否むという結果になるのだから。ペテロの出来事はそれを示している。そして、キリストを否定する人を、神も否定する。神から「あなたを知らない」と言われる事ほど悲しい事は無い。
私達は、ペテロの様に、後悔して泣く事になりたくはない。だから御心を知って、御心を喜ぶ者とならせて頂こう。
2025年8月3日礼拝メッセージ マタイ26:57~68 「沈黙…」 ![]() メッセージは11分半からです。
メッセージは11分半からです。
捕えられた主は、その夜の内に裁判にかけられた。それも不当な悪意に満ちた裁判だ。そんな状況の中にペテロは潜り込んだ。神の御心・十字架を受け入れられないからこそ、主を助けたい(生きていて欲しい)と思ったのだ。だがそれは決して「勇気がある」とは言えない。
さて、宗教指導者達はイエスを訴える偽証を求めた(59)。実は、イエスに罪は無いと分かっているからだろう。勿論、偽証は証拠にはならないが、最後の二人が本当の事を証言した(60~61)。そこで大祭司が問い質すが主は答えない。これを、ある人達は「沈黙の美」と言う。「元々不当な裁判なのだから真面目に答えても仕方がない。沈黙こそ最も理に適った事である。だからあなたも、この主の姿に倣え」と言うのは暴論だ。それなら冤罪も受け入れて、潔白を主張するなという事か。そもそも主は沈黙を貫いてなどいない。「あなたはキリストか」という質問にははっきりと答えている(62~64)。では何故、偽証・誤解に対しては弁明しなかったのか。それは、神の計画・十字架を妨げない為だ(53~54参照)。つまり、十字架にかかる為に、あえて言わせておいただけという事だ。イザヤ53:7は、それを預言していたのである。沈黙は美徳、クリスチャンはそうあるべき…等ではない。
とにかく主の厳しい主張に対し、カヤパは「冒涜だ」と叫び、その主の発言が決め手となって死刑が確定した。しかしながら、主の発言のどこが「冒涜」なのか。神の子を名乗ったからか。しかしそれはカヤパが言った事だ。主も「それはあなたの言った事です」(新共同訳)と言っている通りだ。だから結局、カヤパを怒らせたのは「主が裁き主として来る」という部分(64)だ。言い換えるなら、今イエスを裁いているカヤパを、やがて主が裁くという事である。それでカヤパ達は「もう、どうでもいいから殺せ」となったのである。
ペテロと宗教指導者達は、立場は違えど、どちらも神の御心を拒んでいる。十字架を理解せず、道徳ばかりを語るキリスト教もだ。確かに「イエスは神の御子キリスト」とは言うが、それはカヤパも口にした。それは単に口にしただけなのか「本当の所はどうなのか」は再臨の主が裁くだろう。私達は、主の再臨の時に御心に適う者でありたい。
2025年7月27日礼拝メッセージ マタイ26:45~56 「預言・計画・御心…判別」 ![]() メッセージは12分過ぎからです。
メッセージは12分過ぎからです。
心は燃えていても肉体は弱い…それは、睡魔に負けるという意味ではなく、肉の弱さのゆえに神の御心を拒みたくなるという事だ。そんな誘惑に陥らないように祈るべきなのだが、弟子達はそれが出来なかった。つまり弟子達は誘惑に立ち向かう準備が出来てない(御心を拒む心のまま)なのだ。なのに、時が来てしまった。主にとっての「時」は十字架だが、弟子達にとっては、誘惑との戦いの時である。勝算は、ある訳が無い。だが行くしかない。「裏切る者が近付いた」のだから。
やって来たのはユダと大群衆。皆、寝返った人達だ。特に群衆は剣や棒を手にしている。イエスが奇跡を行う事を知ってるからこそ恐れているのだ。だから、奇跡を見て信じる人もいるかもしれないが、むしろ、奇跡を見ても本当には信じない人が大多数なのだろう。
さてペテロは、相手を本気で殺す気で脳天を狙って剣を振り下ろした。大暴走だ。当然、主は制止する。そして切り落とされた耳を直してやった。敵をも愛したという事だろうか。いや、ペテロの暴走を帳消しにする為だ。ペテロを庇う理由は3つ。「剣を取る者はみな剣で滅びる」(52)、「ペテロの力を借りるまでもない」(53)、「神の御心・計画を妨げてはならない」(54)からである。特に3つ目「御心を拒まない」という事を弟子達はゲッセマネで会得出来なかったので、主はこの土壇場でも弟子達を庇ってやらなければならなかったのだ。その主の計らいも空しく、弟子達は「預言(神の計画・御心)が成就する」との主の言葉を聞いて、主を見捨てた。「預言が成就する」と聞いて、逃げたのである。御心を拒みたくなる誘惑に見事に陥っているのだ。
結局、御心は受け入れるべきという事である。ただ、その為には、御心かどうかの判断が重要だ。サタンの惑わしもあるし、自分の勝手な願望を「御心だ」と都合よく思い込むという事もある。だから、正しく判断する(すなわち誘惑に陥らない)為に、霊的に目覚めて祈れと主は言われたのだ。そして、御言葉によって判別出来る(ヘブル4:12)。
その御言葉を、どこまでしっかりと掴めるか、である。文字面だけとか、通り一遍の理解だけでは、掴めたとは言えない。真理を掴まなければならない。「真理があなたを自由にする」のだから。
2025年7月20日礼拝メッセージ マタイ26:36~44 「誘惑」 ![]() メッセージは14分過ぎ頃からです。
メッセージは14分過ぎ頃からです。
ゲッセマネにおいて主は弟子達に「一緒に目を覚まして祈っていなさい」と言われた。「十字架という苦しみを乗り越える為には、主でさえ、執り成しの祈りが必要だったのだ」と言われる。だが結局、弟子達は眠りこけ、祈らなかった。なのに主はちゃんと十字架にかかられたのだから、執り成しなど必要ではなかったという事になる。では何の為に「祈れ」と言われたのか。明らかなのは「誘惑に陥らない様に」だという事だ。ただ問題は、どんな誘惑の事を言っているのかである。そこに、ゲッセマネの祈りの真実がある。
一方「ゲッセマネの祈りこそ祈りの神髄」と言われる。つまり「私の願いではなく御心を成して下さい」という事だ。しかしながら、御心を受け入れるのは時に茨の道である。主御自身それをゲッセマネで経験されたし、主の母マリヤしかりである。だからポイントは、神の御心が行われる事を喜ぶ事が出来るのか、である。例えば、世の終わり。それは突如、たちまち、一気に、来るというのが御心だ。それを喜べるか…いやむしろ、ゆっくり、じわじわと来てくれた方が助かる。色々準備が出来るから。もし、明日という事になったら「一か月待って下さい主よ、明日、新会堂の献堂式ですから!」と思うかもしれない。それは、極端に言えば、御心を喜べない…という事だ。全てを失っても「御心が成りますように」と祈る…そんな境地に達するのは簡単ではない。主も苦しまれた。誘惑に。
主にとって「荒野の誘惑」に並ぶ誘惑、それがゲッセマネ。すなわち、十字架を避けたい…という誘惑だ。十字架にかかる為にこの世に来られたはずなのに、である。それこそが「心は燃えていても肉体は弱い」という事なのだ。誘惑とは、眠気の事などではない。どれ程「神に従う」と固く決心しても、それでも神の計画に「待った!」と言いたくなる…それが誘惑なのである。その誘惑に陥らない様に、霊的に目を覚まして(神の御心・計画を知って、それを受け入れられる様に)祈らなければならない。それが弟子達にも必要だから「祈れ」と言われたのである。祈りの助けが欲しかったのではない。私達も誘惑に陥らない(御心を良しと出来る)様になれればと願おう。
更なるバックナンバー(要約)は、順次、ブログに移行。