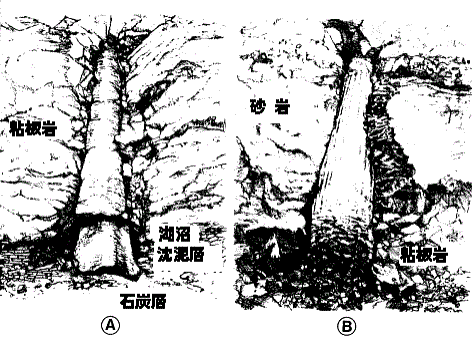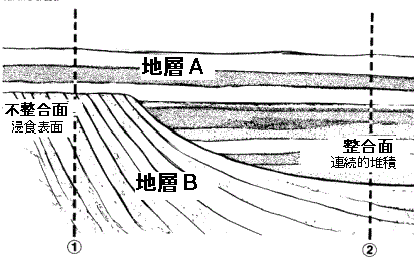「大 洪 水」
− 聖書的地質学 −
[Henry M. Morris, The Biblical Basis for Modern Science, Chapter 11 "Overflowed with Water" (Grand Rapids: Baker, 1984)]
翻訳:千田俊昭(2002.05)
聖書における地質学
懐疑論者が聖書の信頼性を失わせようとする時、そのための最も効果的な科学分野として用いてきたのは地質学、つまり“地球科学”でした。地球の構造分析は特に岩石、それも化石を含む地殻上層部にある岩石の分析によって行われるわけですが、この構造分析の中に、地球の起源と“歴史”に関する自然主義的視点がかなり巧妙に組み込まれており、聖書に書かれていることと非常に異なっているのです。
しかし、地層の形成過程、つまり地殻と地層の特性に影響を及ぼしている物理的プロセスはすべて聖書の記述と合致しています。こうしたプロセスで最も重要なものは堆積ですが、化石を含む岩石はどれも地球の歴史を解読する上で非常に大切です。それらはすべて風化・移動・沈殿・堆積・石化したものだからです。堆積岩は通常、粘土や泥、砂、小石あるいは玉石などを含んでいます。それらは普通、水(時には風や氷)によって浸食され、運ばれて水流が弱まる所に沈殿します。時間とセメント的働きをする媒体、あるいは長期にわたる高圧によって、柔らかい堆積物は硬い岩状のもの、たとえば頁岩(けつがん)、粘板岩、砂岩、礫岩(れきがん)、石灰岩になります。
聖書に散見されるこうしたプロセスに関する言及例としてはたとえば、次のようなものがあります:「しかし山は倒れてくずれ、岩もその所から移される。水は石をうがち、大水は地のちりを洗い去る。このようにあなたは人の望みを断たれる」(ヨブ14:18,19)。「人は堅い岩に手をくだして、山を根元からくつがえす。彼は岩に坑道を掘り、その目はもろもろの尊い物を見る」(ヨブ28:9,10)。また、聖書は地震や火山の噴火といった、もっと目を奪うような地質活動についても多数言及しています。
しかし聖書研究上もっとも重要な地質学的視点はその歴史面です。というのは地質“歴史学”者は地質とそこに含まれている化石を調べることで、地球とその生息していたものを解読することができると公言しているからです。こうした仮説に基づいた地球史は聖書の最初の章と明らかに食い違っているので、私達はまず地球の歴史と実際に関係する聖書的科学的な根拠を少し詳しく考察する必要があります。
地質“歴史学”の非科学性
歴史家でも地質学者でもない多くの人々にとって、地質歴史学(historical geology)の研究は非常に興味を駆き立てられるもので、この分野は人間の思考の中で特異な関心と重要性を占めています。人文科学において「歴史」の研究は確かに際立った重要性を持っていますが、科学において「地質学」はそれが地球自体を扱うものであるだけに、同様に独自の関心を惹きつけます。その両者が組み合わされた「地質歴史学」は、地球の起源と生成過程史の謎を解読するものだと公言した結果、とんでもない関心と重視を引き起こしたのです。このような有り様は実際のところ、歴史学的にも地質学的にも行き過ぎた状態です。あるものの起源に関する説には必ず思想的・信条的傾向がつきまとい、そこには意味や目的、到達点といったことに関する強度の恣意性が伴うものです。
地質歴史学が実に様々な人々の強い関心と興味を引き起してきたということは別に驚くに値しません。実のところ現代の地質歴史学の基礎的構造は100年以上も前に次のような人々によって作られたのです:ジェームズ・ハットン(医学的訓練を受けた農学者)、ジョン・プレイフェア(数学者)、ウィリアム・スミス(測量技師)、チャールズ・ライル(法律家)、ジョルジュ・キュヴィエ(比較解剖学者)、チャールズ・ダーウィン(神学生、博物学者)、ロバート・チェンバーズ(ジャーナリスト)、ウィリアム・バックランド(神学者)、ロデリック・マーチソン(兵士、愛好家)、アダム・セジヴィック(この人物はケンブリッジ大学で地質学会議長職の選挙にあたって、自分は地質学については何も知らないと豪語した)、ヒュー・ミラー(石工)、ジョン・フレミング(動物学者)、その他同様な人々。
これらの人々の手になる地質歴史学の基本的枠組みは今日に至るまで変更されていませんが、今や一群の専門的地質歴史学者が登場してきて、この分野を自分達の専門科学領域と考え、定説となっている体系(訳注:地質年代決定システムのこと)に異を唱えようとする、いかなる発言や著作をも蔑視しています。しかし地質歴史学はその性質上、純正な科学たり得ないので、その創設者と現代の指導者の解釈に追従するような独善的主張は、起源や意味論に含まれる恣意性と相まって、とても科学と呼べる代物ではありません。地質歴史学は地質学の訓練を受けた人々によって設立されたものではない以上、非地質学者と地質学者の両者によって評価・批評されるのが道理であると思われます。
これは科学としての「地質学」を非難しようというのではありません。地質学は文字どおりの科学であって、私達が自然法則を理解・適用するのに多大の貢献をしてきました。しかし地質学者(あるいは、法律家や測量技師、博物学者、その他誰でも)が、地質歴史学者になりたがるとき、彼は科学の領域を去って思想や信条の領域に入るのです。地質歴史学において現在定説となっているシステムは基本的には進化論的「斉一論」(せいいつろん uniformitarianism 訳注:過去の地質現象は現在も地球上で起こっている諸現象と同じ過程で形成されたとする説)という思想ないし一種の信仰以外の何ものでもありません。このことは科学者による一般的研究および地質学者による特別の研究によって示された物理的プロセスの本質を考察するにつれて、より明らかになるでしょう。
もちろん「科学」(science)という言葉そのものはラテン語で「知識」を意味する scientia から派生したものであり、これがその本質を表わしています。より公式な定義としてオックスフォード辞典では次のように述べられています:「学問の一分野。関連性をもった実証済みの真理、もしくは観察され体系的に分類され、一般的法則の下に総括された事実にかかわる学問であって、その領域における新しい真理を発見するための信頼しうる方法論を包含する。」
このように科学は観察された事実と実証された法則にかかわるものなのです。科学的方法は因果関係のように実験による再現可能性にかかっています。科学は知識であって、推論や推測、推定ではありません。
本当の科学というものは現在の現象とプロセスを測定し研究することに必ず限定されるものです。現代において観察されてきたデータまたは過去の歴史上の人間によって観察されたデータが科学的データと呼ばれるにふさわしいものです。このようなデータから導き出されてきた法則やデータを適切に関連付けるような法則、また将来の実験などから得られる類似データの関連性を予測することができるような法則こそが科学的法則なのです。
ところがこうしたプロセスや法則が過去において常に同じだったのかどうか、また未来においても常に同じかどうかについては知るすべがありません。もちろんこの種の仮定をすることは可能ですが、実はこれが斉一論としてよく知られている説なのです。この仮定はなるほど現在のプロセスに関する私達の経験に照らしてみればあてはまり、それに基づいて未来や過去についてもある程度の期間あてはまると推測してよいことは疑いありません。しかし、斉一論だけが過去と未来の全てを理解する唯一の科学的アプローチであると主張することは教条主義に陥った一種の信仰以外の何物でもありません。
斉一論がこれまで地質歴史学の基盤をなす指導的原理となってきたことは広く知られています。ある標準的な教科書ではこの項目について、たとえば次のように述べられています:
「こうした空想的信仰(つまり天変地異説のことをさす)の根絶はスコットランドの地質学者ジェームズ・ハットンが1785年に出版した「地球理論」に始まるが、同書で彼は“現在は過去の鍵である”ということと、充分な時間が経てば現在進行中のプロセスは地球のすべての地質的特徴を説明することができるだろうと主張している。この思想はやがて斉一論として知られるようになるのだが、膨大な時間を必要とする。それは今や知性ある識者に広く受け入れられるに至っている [Carl O. Dunbar, Historical Geology, 2nd ed. (New York: John Wiley and Sons, 1960), p.18]。
真の科学が扱うのは実験によって計測することができ、観察によって検証することができる現在のデータとプロセスです。斉一論の本質は思想ないし信条であり、それによってこれら現在のプロセスがはるか昔や未来の出来事すべての発生を説明することができると仮定するわけです。
しかし用語という点から見ると、明らかに斉一論は証明されたものではない以上、科学の定義には合致しません。そのような仮定の基礎になる仮説がほかにいくつもあって、それら全ても同様に単なる信条的なものでしょう。
他方で次のように仮定することはまったく可能かつ合理的なことです。つまり、科学が研究している地質プロセスは過去のある時期に始まったのであって、将来いつか終焉するかもしれないと仮定することです。ただ、そのプロセス自体は始まりと終わりについて何も語ることはできません。これは科学的調査の領域外のことでしょう。こうした情報がもたらされ得るとすれば、それは創造主なる神の啓示によるほかはありません。
真の斉一論
斉一論という概念そのものは合理的な枠組みをもって使われるならば完全に有効であり適切なのですが、地質歴史学において極めて非合理的に適用されてきたのです。真の斉一論は自然法則(特に熱力学の法則)の不可侵性にかかわる立場であって、進行速度の一様性ではないのです。熱力学の法則が示していることは自然界のプロセスの性質はどうあるべきかということですが、そうしたプロセスの速度がどれだけ速いか遅いかということは示していないのであって、進行スピードが常に一定であるという保証はどこにも存在しないのです。
しかしこの斉一性(プロセスの進行スピードが一定であるということ)こそが、地質歴史学に適用されてきた、まさに枢軸原理的な仮説なのです。それはこの原理に関する次のような、かなり典型的な記述の中に明らかです:
「こうした考え方に反対しているのはチャールズ・ライル卿(1797-1875)である。彼はキュヴィエと同時代の人だが、地球の変化は現代と同様な均一的遅さで徐々に起きたという立場を取った。ライルはこのようにして多かれ少なかれ、地質学的思考を導いてきた「現在は過去の鍵」という仮説の提唱者とされている。要するに、ライルの斉一論によれば、過去の地質的プロセスは現代と同じ速度で起こったということである」[James H. Zemberge, Elements of Geology, 2nd ed.(New York:John Wily and Sons, 1963), p.200]。
もし地質運動の速度が常に今日のようなものであり続けたとする仮説に立つならば、地球の年齢が非常に古くなることは明らかです。地質プロセスの年代計算にはたくさんの方法があります。放射性同位元素崩壊度測定、大陸浸食、峡谷形成、三角州堆積、海洋ナトリウム増減測定、その他 ── 現在の速度を基準にするということはもちろん最も重視されざるを得ないのですが、聖書的年代という枠組みからかけ離れたものになってしまいかねません。
しかしそのような均一なプロセススピードを仮定する科学的根拠は存在しません。流水が土壌や岩を浸食し、放射性元素が減衰するといったことが不可逆性のプロセスをたどると推測することは熱力学の第二法則に則していて正しいのですが、だからといってその進行スピードが常に緩慢であって一定であるとする保証は何もなく、そのような科学法則も存在しないのです。事実、確かなことはそのような崩壊過程は非常に複雑に入り組んでいて、実に多くの要素(そのうちのたった一つの変化でも進行スピードにかなりの影響力を及ぼしうる)が関わっているので、実験上確認された諸条件が正確に分かっているのでない限り、速度を正確に割り出すことは永久に不可能なことでしょう。
創造論者(creationists)と聖書的天変地異論者(Biblical catastrophists)が長い間主張してきたこの点に関する峻別を、近年多くの地質学者が受け入れ認識してきたことは喜ばしいことです。スティーブン・J・グールド博士は影響力を持った進化論者ですが、真の斉一論と誤った斉一論を最初に区別し始めた学者の一人であり、彼はそれぞれを「方法論的斉一論」(methodological uniformitarianism)と「実質的斉一論」(substantive uniformitarianism)と呼んで区別し、次のように述べています:「斉一論には二種類ある。実質的斉一論(地質変動に関し、速度と物理条件が一定であると仮定する検証を必要とする理論)は論点搾取の誤りを犯している。方法論的斉一論(自然法則の空間的時間的不変性を主張する手続的原理)は科学の定義にあてはまるものであって、これは地質学に特有なものではない」[Stephen Jay Gould, "Is Uniformitarianism Necessary?" (American Journal of Science 263 Mar.1965), p.223]。
この見解には全く同意します。(天地創造が終了して以来)自然法則の斉一性は科学の基礎であって、それは聖書とまさしく調和しています。(もちろん、創造主が望まれる時は、奇跡によってそうした法則を阻止する予知は常に存在します)。しかし、ここ100年にわたって揺れ動いてきたタイプの地質学的斉一論は、実は現代の進化論に基礎を提供してきたのですが、単に聖書の記録に反するばかりでなく、実際の地質的データを説明するためにも不適切なものなのです。「実質的斉一論は現象を説明する理論としては新しいデータの検証には耐え得ないもので、もはや厳密には理論とは言えない」[同書, p.226]。
伝統的な地質学的斉一論はもはや維持され得ず、また真の意味の斉一論は地質学に特有なものではない以上、斉一論を地質学理論に固有のものだとすることは誤りです。ではなぜそのような固有論がいまだに行われているのかということの理由が以下の引用箇所にはっきりと示されています:「専門用語としての方法論的斉一論が有効なのは、科学がその分野における超自然的状態を論議する場合だけである。なぜなら、もし神が介入するならば、法則は不変ではなくなり、帰納は無効になってしまうからである。…今日においてこの用語は過去の遺物である。というのは、そのためにわざわざ骨折ったとしても、われわれの研究の科学性に寄与するものはもはやないからである」[同書, p.227]。こうした推論の表面下に見て取ることができるのは、本当の問題は実は科学ではなく、科学“主義”だということです。つまり、地質歴史学者は実質的斉一論(変動速度不変説)を擁護しようとして、議論の余地がない方法論的斉一論(自然法則不変説)の証拠を引用してきたのだということです。推論上のこの誤りが意識的だったのかどうかは取るに足りないことで、いずれにせよ、その根底にある動機は創造主とその歴史的介入を可能な限り昔のことに押しやり、その上できれば神も除き去りたいという内心の思いです。起源と発達についての十全な思想(というよりはむしろ一種の信仰)はこのようにして、誤まれる斉一論の上に建てあげられているのです。
実質的斉一論を疑問視する地質学者は以前から多かったのですが、グールドの説得力ある筆致が触媒となって、「天変地異説」(catastrophism)の復興を引き起しました。この「自然主義的新天変地異説」(naturalistic neocatastrophism)が進化論的生物・地質学上の新しい「断続平衡学派」(punctuated equilibrium school)(これはグールドも強く提唱している)と組み合わされて、従来の遅行性の地質変動と生物進化論に急速に取って代わっているのですが、実のところ、かつては見捨てられていた理論なのです。
アメリカ地質学会の公式出版誌最近号の注目すべき記事の中で、地質学者のジェームズ・シーアは地質学上の先人たちの斉一論における誤謬を長いリストにして数え上げ発表しました。とりわけ次の批評は注目すべきです。「さらに、ライルの斉一論の大部分、特に古代と現代の原因の同一視とか漸進説(gradualism)および、速度均一説(constancy of rate)といった彼の主張は現代の明らかなデータによって論駁されているだけではなく、圧倒的多数の証拠は実質的斉一論がそうであるように、これらの事柄に関して彼の理論が単純に間違いであることを示している」[James H. Shea, "Twelve Fallacies of Uniformitarianism," (Geology 10, Sept.1982) p.456)。この後に彼は次のように続けています。「地質運動の速度や集中度が均一であり続けているという説は明らかに証拠に反しているので、誰でもその一貫性に戸惑いを覚えざるを得ない」(同書,p.457)。
古生物・鉱石経済学会(Society of Economic Paleontologists and Mineralogists)の会長には、指導的地質学者でウィスコンシン大学教授のロバート・ドットが最近就任しましたが、その会長就任演説において彼が強調したのは、堆積岩に保存されている地質の記録は局地的天変地異であって、遅行性で速度が均一な堆積ではないということでした。たくさんの証拠と例を挙げた後で彼は言っています、「沈殿層という記録はその大部分が挿話的出来事の記録であって、継続的斉一性を示すものではないということを納得していただきたいのです。私がお伝えしたいのは、挿話性が原則であって例外ではないということです」。彼が「天変地異説」ではなく、「挿話性」(episodicity)という単語を使っている理由には興味を惹かれます。なぜならそれは創造論への募る恐れを表しているからです。「“挿話性”という言葉は他の表現も可能だとは思いますが、慎重に選び出された表現です。近ごろは“天変地異”という語が劇的な効果を持っているために流行しているようですが、それは新天変地異主義に立つ創造論に口実を与えることになるので、追放すべき言葉です」(同書)。しかし現代の「挿話論者」も「天変地異論者」もライルの斉一論と結び付いた従来の地質年代システムの基準に依然として追従しているのです。彼等は各地質年代を真正で長期にわたるものだと見なしていますが、地質年代を示すとされる地層はすべて急速に形成されたものなのです。このように、こうした新しい説によっても、ほとんどの推測されている地質時代というものは、それについての文書記録が全く残されていません。
デレク・アガーも新天変地異論に立つ現代の地質学者ですが、彼は次のように述べています:「しかし、私が主張しているのは、地層相位学的記録のはるかに正確な現況は、それがかなり突発的な沈殿を伴った一つの長いギャップを持っているということだ」[Derek Ager, The Nature of the Stratigraphical Record (New York: John Wiley and Sons, 1973) p.34]。アガー博士は英国スワンシーにあるユニバーシティ大学の地質・海洋学の主任教授です。彼にはこのテーマをめぐる広範囲の著作があり、その主張はあらゆる地質の形成と構造が天変地異の記録である、ということにあります。しかし彼はこのような結論が創造論者的に受け取られかねないことを気遣い、自分がそれとは無関係であることを明確にしようとして次のように言っています:「ファンダメンタリストが本書を自分の偏見を補強するものとして読むことがないように、私はカテゴリーに分けて述べておきたい…つまり、私は神による宇宙創造とかいったものは全く不必要な仮説だと分かった。ただそれだからといって、化石という記録にはいくつかの非常に奇妙な特徴があるということを否定するものではない」(同書 p.19)。
ドットやアガーのような現代の自然的天変地異論者が地質年代システムを護持したいのは、進化にとってそれが極めて重要だからです。進化が蓋然性を持つには長い時代が必要であり、そのために標準的な地質年代システムは不可侵と見なされているのです。しかし、実際の地層はすべて短期間で急速な堆積があったことをはっきりと示しています。
進化論の枠組み
斉一論原理によって恐らく示唆されている地球の途方もない歴史は、一連の地質時代に細分化され、程度の差こそあれ標準化されており、それぞれの時代は通説的な名前とおおよその長さが与えられています。その全体の順序は地質年代表(Geological Column)として知られているもので、それは時代的には地質時代区分(Geological Time Scale)(下掲の表1を参照)に対応しています。もちろん、それこそがいわゆる地質歴史学の背骨なのです。どんな岩石形成層であろうとも、その表のどこかにあてはめられ、その時代区分によって形成された時期を決められることになっているのです。
この点に関して、ある適切な(ただ、中にはそれを不適切だと考える人もいるわけですが)質問が問われなければなりません。多様な岩石や地質構造は何を基準にして分類されるのか?デボン紀とかオルドビス紀といったものは、どのようにして割り当てられるのか?どちらが古いとか新しいとかはどのようにして分かるのか?連続した時代の区切り目はどのようにして分かるのか?
層位学的分類に関するこれらの問題は現在の形の地質年代表が百年以上にもわたって、一般に承認されているにもかかわらず、曖昧さと論争の中に封じ込められています。
専門家でない人々に見られる傾向は、積層の法則(訳注:地層は下に行くほど古くなるという原則)が相対的年代決定の主要素であって、異なった地域にある地層もその中に含まれる化学的成分や堆積物質によって同時代のものかどうかが分かると推定することです。しかし、これはそうではないのです。一つの地層の年代決定にとって最も重要な要素はその中の生物含有物、つまり化石なのです。「こうしてみると、現在において唯一利用できる合理的な地質年代的指標は生物層位学的、つまり生物年代学的基準のように思われる」[T.G.Miller,"Time in Stratigraphy," (Paleontology 8 Feb.1965), p.119]。これは明らかに次のことを意味しています。つまり、ある堆積層が地球史上のどの時代に属するかを決定する唯一の基準は化石だけであることになります。その他のデータ、つまり縦方向の位置とか、物理化学的特性、あるいはその他の要素は本質的に重視されないのです。
<表1>標準的地質「年代」の区分
この標準的とされる地質年代は、地球の堆積層と化石層を垂直的・仮説的につないだものを表していますが、実際上は地球のどの単一地点にも発見されたことがありません。これは単に様々な地点を積み重ね補完して人工的に構成したものです。
地質年代の主要区分と出来事 |
代
|
紀
|
世
|
出来事
|
推測年代
|
新
生
代
|
第四紀
|
沖積世
洪積世 |
現代の動植物や人類の
出現 |
25,000
975,000 |
第三紀
|
鮮新世
中新世
漸新世
始新世
暁新世
|
哺乳類や被子植物の
出現
|
12,000,000
25,000,000
35,000,000
60,000,000
70,000,000
|
中
生
代 |
白亜紀 |
アンモナイト、恐竜の絶滅 |
70,000,000
〜
200,000,000 |
| ジュラ紀 |
有袋類、始祖鳥、昆虫類の出現 |
| 三畳紀 |
アンモナイト、爬虫類、裸子植物の出現 |
古
生
代 |
二畳紀 |
原始的爬虫類、シダ類出現;三葉虫の絶滅 |
200,000,000
〜
500,000,000
|
| 石炭紀 |
胞子植物、最古の昆虫類の出現 |
| デボン紀 |
最古の種子植物、海生無脊椎魚類、両生類 |
| シルル紀 |
動物の上陸、魚類、サンゴ、三葉虫 |
| オルドビス紀 |
最古の脊椎動物、植物の上陸 |
| カンブリア紀 |
無脊椎動物 |
| 原生代 |
原始的な水性動植物 |
500,000,000
1,800,000,000
|
始生代
|
最古の生命体(間接証拠のみ)
|
ある岩石がどれくらい古いかを示すことができる唯一の方法は、その中に含まれている化石が地球の歴史上のどの時代に生きていた生物なのかということだけにかかっています。これでは歴史上異なった時代には異なった種類の生物がいなければならないことになり、従って化石は時代区分のためには曖昧な指標にしかなりません。
しかし地質学者はどのようにして、どの生物がどの時代に生きていたと決定するのでしょうか?地質時代の経過に伴う生物の形態変化を観察し分類する系統だった方法が存在しなければなりません。その鍵になるのが当然、進化論なのです。もしすべてが斉一論的法則とプロセスによって説明されなければならないのだとしたら、生物世界や物質世界の発達も含まなければなりません。従ってあらゆる種類の動物は初期の単純な形態から徐々に発達してきたのでなければならないことになります。地質史の間に器官や生物形態の緩慢な増加がなければなりません。
このように、化石という記録は地質上のデータとして、この上なく重要なのです。しかし多くの化石が複数の「時代」に見出されるので、「標準化石」として知られている或る種の化石だけが年代決定の目的で使われています。「おのおのの地層においてはある化石が特徴的に豊富であるように見受けられるのであり、これらの化石は標準化石として知られている。年代の分からないある地層に、もし標準化石が発見されるならば、その特定の地層や岩石を決定するのは容易であり、同じものを含む露出層が遠く離れた地域にあったとしても、両者を関連づけることができる」[J.E.Ransom, Fossils in America (New York: Harper & Row, 1964), p.43]。この方法の進化論的特徴は以下の文によって明らかです:「それぞれの化石は生物が実在したことを表しているのであって、特別に創造されたものではないということが一旦理解されれば、次のことがきわめて明瞭になる。つまり、離れた地層のそれぞれに含まれている動植物は単純に前の時代から徐々に適応して進化したのである。それらは順に下のものがその後のものの先祖なのである」(同上)。
このテクニックはもしそれが歴史的記録とか神的啓示あるいは他の情報源から、生物はすべてそれに先立つ形態から実際に進化した、と知られるのであればメリットがあるかもしれません。しかしこうしたスケールでの進化の実際的証拠は、先の引用が意味しているとおり、残存化石に限定されるのです。アメリカ考古学会における会長演説でホリス・ヘッドバーグ博士は化石の進化論的重要性について次のように強調しました:
「改めて申し上げる必要もないことですが、地層の順位に関する現代の私たちの知識はその大部分を化石証拠に負っています。岩石を構成する特徴的要素であるというだけでなく、化石は堆積層を跡付け関連性を追う上で最良の手段として広範囲に用いられて来ました。しかし、それだけにとどまらず、地球上の進化の記録として、化石は大陸間に分断されている地層の関係を探る驚くべき鍵を提供してきたのです」[H.D.Hedberg: "The Stratigraphic Panorama," (Geological Society ofAmerica Bulletin 72, Apr.1961) p.499-518]。
このように地質年代表において相互に関連する岩石形成層の年代を決定する第一の要素は、各地質時代に地球上に生きた生物の進化論的順序であり、それぞれの時代の岩石に堆積し、化石として保存された特徴的な生物なのです。地球の進化の歴史は連続する地質時代を代表する岩石という記録に基づいて組み立てられてきました。実際、進化の事実を証明する歴史的証拠として唯一純正なものは、この化石という記録以外には見つかりません。ダンバーは言っています:「現存する動植物の比較研究によって、非常に説得力のある状況証拠が得られるかもしれませんが、化石は生物が単純なものから徐々に複雑な形態に進化したという歴史的で記録的な唯一の証拠なのです」[Dunbar, Historical Geology, p.47]。
現存する動植物から得られる進化の証拠は確かに確証からは程遠いでしょう。進化的変化を引き起す生物学的メカニズムとして、ほぼ一般的に受け入れられているのは、遺伝子の突然変異が自然淘汰によって保存されるようになった場合だろうと思われています。しかしながら、ほとんどの遺伝子学者が認めているのは突然変異は基本的に有害だということです。なぜ必ずそうなのかというと、突然変異は既存の高度な秩序をかき乱す変化を意味するからです。
事実、突然変異は熱力学第二法則のうってつけの例示です。というのは、宇宙は混沌と崩壊に向かう傾向を示しているからです。ともあれ、真に有益な突然変異というものが仮にあったとしても、それが非常に稀であることは明かなので、現在の動植物に本当の進化が起きたかどうかを知ることはほとんど不可能なのです。もちろん生物の基本種内部でも実に様々な種類があるわけで、実際に同種のものでも、全く同一の個体というものはありません。しかし、それでも生物種相互の間には明確な境界が存在します。
進化は現在起きている事として証明できないものであり、いま存在していて証拠づけ得る生物的変化は成長や器官の進化ではなく、むしろ崩壊と死であるので、明らかに広義の進化的証拠は唯一、化石記録に含まれているものだけなのです。
しかし、化石の年代は地質年代に基づいており、地質年代は地球の歴史を解釈する枠組みとして組み立てられているのですが、それは暗黙の内に進化論に基づいていて、これは下図1のように循環論法になっています。ただし、すべての思想は結局、循環論に基づいているので、それ自体は責められるべきことではありません。誰でも起源や意味を思想化しようとするならば、ある内在的前提を持ち出してきて、それが必然的に結論となるのですから。しかしそれでは「科学」ではなく、科学主義になってしまいます。宗教的な信条にはなり得ても、科学ではありません。それだけではなく、そのようなシステムが問題や矛盾に直面すると、すべての特殊ケースを包含しようとして、さらなる修飾や拡張が必要となるのです。今こそそのシステムが依拠している基本的前提を検証すべき時です。俎上に乗っているのは循環論法をもった進化論的年代システムなのです。
<図1「循環論法」>
進化の中心的証拠は、より古い岩石中のより単純な化石です。しかし、岩石の地質年代はその中に見出される時代を表す化石の集合によって決定されます。このような標準化石に割り当てられる地質年代はその進化の度合によって決定されます。こうした論理に内在する循環論法は明らかに進化ということが絶対にして侵すべからざるものと見なされていることを表しています。
聖書的地質学
進化論的斉一論が地質歴史学の枠組みとして不適切であるならば、それに代わるより良い枠組みが必要となります。通説的な地質学的時系列が本当に循環論法と進化論の仮説に基づいているのであれば、岩石の堆積や化石年代の順序に関するより良い説明が必要となってきます。聖書という太古の地球史に関する記録が、実は地質学的な実際のデータ全てを相互に関連させる上で、はるかに実効的なモデルを提供しており、その主要な鍵となるのは創世記6−9章に詳説されているノアの時代の大洪水なのです。
実際に初期の地質学者のほとんどが信じていたのは、地球の堆積岩や膨大な地層が化石を含んでいるのは聖書の伝える洪水が原因だということでした。そうした人々にはたとえば、「層位学の父」と呼ばれるニコラウス・ステノとかケンブリッジ大学に古生物博物館を創設したジョン・ウッドワードなど、このほかにもたくさんいます。アイザック・ニュートン卿はおそらく歴史上最も偉大な科学者でしたが、彼はウッドワードの親しい友人であり、聖書の述べる天地創造と大洪水を信じていました。
ところが18世紀の終り頃までに、バフォンやプレイフェア、特にジェームズ・ハットン、さらにチャールズ・ライルといった人々によって、長年月の地質年代説と斉一説が提唱されたのです。同じ頃、他の人々によって天変地異説を修正した説が主張されました。聖書が教える世界規模の大洪水の代わりに「複数の天変地異」がジョージ・キュヴィエによって強く提唱されたのです。
19世紀の中葉までにはライルの斉一説がキュヴィエの天変地異説を陵駕し、ダーウィンの進化論への道が完全に準備されました。ダーウィンは自然淘汰による漸進的進化という彼の理論が地質学的斉一論の提唱する長年月に及ぶ緩慢な変化という仮説に依存しているということをはっきりと認識していましたが、この理論体系が知識人の全面的な支持を得るに至ったのです。
聖書の神学者達は残念ながら、この発展に取り乱し、進化論や地質年代に迎合する聖書解釈論を編み出そうとさえしました。多くの人が進化論を「神による創造の方法論」とまで賞賛し(「神学的進化論」)、そしてそのために必要となる膨大な時間については、六日間の創造に関する創世記の記述を地質時代の枠組みに対応するものと解釈したのです(「一日一時代説」)。中には創世記冒頭の2つの節の間には間隙があって、ここに地質時代がはさまれるのだという神学者まで現れました(「間隙説」)。
しかしそうなると、なんとか片付けなければならないのが、聖書の洪水記録です。もしそのような洪水が実際に起きたのだとすると、斉一論や長年月の時代といったシステムが崩れてしまうからです。このようなわけで、妥協的な神学者達の中には、じきに局地的洪水説を唱える者や、地球規模ではあっても、それは静的な洪水だったと言う者もありました。しかし実際のところ、局地的洪水説はまったく反聖書的であり、静的洪水説は馬鹿げていて用語矛盾です。
聖書によれば、ノアの時代の大洪水は全世界的天変地異であり、「その時の世界は水で覆われて滅んでしまった」(2ペテロ3:6)のです。聖書の記述は信頼に足るものであって、意味に満ちているものなので、創世記の洪水は実際に世界規模の天変地異だったのです。
聖書が局地的ないし地域的洪水ではなく、地球規模の洪水を示しているということは様々な理由によって明らかですが、それらは以下の通りです:
1.洪水はすべての高い山々を覆っており(創世記7:19-20)、それは約9ヶ月に及んだ(創世記8:5)。これらの事実は水力学的に世界規模の洪水以外の何ものでもありません。
2.洪水記事(創世記6-9章)において、それが世界規模だったことの表現はたまたま散見されるのではありません。聖書の他の箇所では「世界」という言葉が限定的な意味で使われることがあるのは事実ですが、ここで「世界」は繰り返し使われ、再三再四強調されていて、記述の中心的要素となっています。これらの章においては少なくとも30回にわたって、地球規模を現わす言葉(「すべての人」「すべての生物」「空の下のすべての高い山」など)に言及されています。
3.聖書ではこのあと、洪水が世界規模だったことが前提にされています。特に以下の箇所を参照してください。詩篇104:7;1ペテロ3:20;2ペテロ2:5;3:5-6;マタイ24:37-39。
4.大洪水の主要目的は全人類を滅ぼすことでした。このことは創世記での記述にその趣旨が数多く見られるばかりでなく、ペテロ(2ペテロ2:5)やキリストの言葉(ルカ17:26-27)にも見られます。地球規模の天変地異でなかったならば、この目的は達成され得なかったでしょう。人類が早くから全世界に広がっていたことは人類学の研究によって明らかにされていますが、もっと重要なことは、聖書が洪水以前の人類について、そのきわだった長寿と繁殖性を述べていることです。彼等は何百年にもわたって地に満ちていたのです(創世記1:28;6:1,11)。
5.方舟の途方もない大きさ(それは控え目に見積もったとしても、貨物車500両以上を収容できる容量を持っていた)は、単なる一地域の全動物をはるかに超える数がその中に保管されたということの雄弁な証しです。その目的は「その種類が全地のおもてに生き残るようにしなさい」(創世記7:3)ということにありましたが、もし洪水が局地的なものであったとしたら極めて間の抜けた計画だったことになります。
6.もし大洪水が世界規模のものでなかったなら、方舟の必要性が全く存在しなかったことは明らかです。ノアとその家族が方舟建造に要した120年のうちに、どこか遠くの地へ移住することなど簡単にできたでしょう。同様にその地域の鳥や動物達も移住によって簡単に種族を保存することができたはずです。局地洪水説によるならば、大洪水の物語は馬鹿げたものになってしまいます。
7.神は3度にわたって(創世記8:21; 9:11,15)「わたしは、このたびしたように、もう二度と、すべての生きたものを滅ぼさない」と約束していますが、これは地球規模の大洪水なればこそのことなのです。もしその約束が局地的な洪水のことだったとするならば、これまで起きた局地的な洪水のたびに、約束は破られて来たことになります。従って、局地洪水説は聖書が誤っているとするばかりではなく、神は約束を守らない方だとすることになるのです!以上に述べた7つの理由がすべてではありません。拙著 Genesis Record (Grand Rapids: Baker, 1976), pp.683-86 で、私は洪水が地球規模だったに違いないという100の理由を聖書と科学の見地から挙げています。
ノアの時代の世界的洪水は聖書が強調して教える明らかな歴史的事実ですが、それをもし聖書的クリスチャンがいわゆる科学的困難性があるとして希釈しようとするならば、危険な土俵に足を踏み入れることになります。この事実を否認したり無視したりすることは、創世記の記録のみならず、この記録に関する新約聖書の証言をも否認することを意味します。
他方で洪水が世界的なものだったということを受け入れるならば、直ちに極めて重要な科学的意義に導かれます。たとえば、そのような洪水を引き起こした水は海洋の大幅な潮位上昇によったのか、あるいは現在の大気成分とは全く異なる異常なまでの水蒸気を含む大気があったのかということになります。聖書はその両方の水源に帰しています。40日40夜続いた豪雨(創世記7:12)と、それから更に110日続いた少し弱まった降雨は、恐らく創世記1:6-8「おおぞらの上の水」で示唆されている濃い水蒸気層の凝縮の結果だったと思われます。同時に起きた「大いなる淵の源は、ことごとく破れ」(創世記7:11)というのは疑いもなく、火山活動と地殻や地下水の地殻的上昇が関わって150日も続いたということを表しています(創世記7:24; 8:2-3)。
使徒ペテロは次のように書いています:「その時の世界は、御言により水でおおわれて滅んでしまった」(2ペテロ3:6)。彼が言っている「世界」とは地球とそれをとりまく空を含んでおり、それは次の2ペテロ3:7に言う「今の天と地」とは明らかにまったく異なっています。創世記の記録によると、人間だけでなく地球も大洪水によって滅ぼされました(創世記6:13; 9:11)。この滅びが意味するところは、破壊して完全に消滅させることではなく、地球の表面とそれを取り巻く大気の特性について、水利的・地質的・気象的に甚大な変化があったことを意味しているのに違いありません。
全生物の滅亡という未曾有の出来事が同時に起きた以上、これら動植物の大多数が封じ込められ埋められたことは確かです。そして後にそれが石化して保存され、広大な化石の墓場となったのです。この結論はエデンの呪いという聖書の記録によって更に立証されます。本来の創造は神によって「はなはだよい」と宣言されましたが、アダムが罪を犯したとき神は「地」を呪いました(創世記3:17; 5:29)。このようにして世界に崩壊と死の原則が入り込んだのです。このことと新約聖書でパウロが述べていること(ローマ5:12; 8:20-22; 1コリント15:21)の両方が意味しているのは、この呪い以前の世界には生身の動物や人間の死は存在していなかったということです。
このようなわけで、かつて生きていた生物の化石はそれが地球上のどの岩石から発見されるものであれ、人間の堕落後に死んだ生物のものに違いありません。これはすべての化石を含む堆積層は人類の歴史上のいずれかの時点で形成されたということを意味します。従って、化石の存在を説明するものは大洪水とそれに伴う地質的・水利的活動以外にはありません。
洪水の際の水やその堆積物の動きを考察すると、次のような結論が導かれます。つまり、どの地域をとったとしても、堆積層はある特性を持つということが仮定されるということです。言い換えれば、沈殿層の下部に堆積する傾向があるのは、体重の重いもの、構造の単純なもの、低いところに生息するもの、泳ぎや走行・飛行の遅いものがまず洪水にとらえられるということです。高等生物や高いところに住むものは後になって、上層に埋められることになるでしょう。洪水という天変地異の性質上、この法則には多くの例外の起きることが予測されますが、これは一般的法則であり、地球上の化石層にまさに見られることなのです。
天変地異説の代替理論
天変地異説が地質学的原理に合致するものだということが認識されても、それが想像力をかき立てて、様々な種類の擬似天変地異説を生むことになるのは自然の成り行きです。斉一論の大きな利点や強みは、それによって地質の解釈がこれまでの通説の範囲内で行なえるという点にあったのです。現代の天変地異説でさえも、その激変を人類史上で経験したたぐいのものに限定しようとしているほどです。
しかし制約のない天変地異説にはそうした限定はありません。どのような種類の地質的特性や現象であっても、それにあてはまるような恣意的な異変を仮定すればよいのであって、それを科学的に検証する方法は存在しません。なぜなら科学的観察や実験をするすべのない再現不可能な事柄だからです。制約になりうるものがあるとすれば、提唱者の想像力ぐらいなもので、それによって彼は自分の提唱する異変のメカニズムを、可能な限り広い地質特性に応用し得るものにしようとするわけですが、そのようにして、個別的な場合の検証をさせまいとするのです。
1950年にイマニュエル・ヴェリコフスキーは広く知られることになる数冊の著作を出版し始め、それによって天変地異説の現代的理論を展開しました。それによると、地球は一連の巨大彗星と遭遇し、それらの彗星が後に惑星となったというのです。その当時、この説は斉一主義の科学者たちの間に実に激しい対立をひきおこしたものですが、近年になって多数の同様な擬似天変地異説が発表されており、そのうちの幾人かは科学畑出身です。ヴェリコフスキーの説でさえも、更に真正面から取組む科学者も多いのです。
このような流れを汲むものには、他にケリーとダカイルが強調する巨大隕石影響説、チャールズ・ハプグッドとアイヴァン・サンダーソンによる地殻移動説、ドナルド・パットンによる新ヴェリコフスキー説とも言うべき宇宙遭遇説、メルビン・クックの水冠説、H・A・ブラウンの地軸動揺説、J・L・バトラーの小惑星衝突説、その他にも多くの仮説があります。こうした人々のほとんどは斉一論に対する何らかの特徴的で有意義な反証を付け加えています。それぞれが自分の最も得意とする特定の異変形態によって多くの地形学的特徴を指摘することができるのです。オーソドックスな地質学者たちの中からも新天変地異説が提唱する様々な説を、かなりの程度支持する者が近年現れてきています。それらの説とは、極移動説、大陸移動衝突説、惑星彗星遭遇説、広範囲洪水説、海岸線急激変化説、造山運動加速説、海底地滑り説、その他多数。天変地異があったという推測は近年認める人が増加しており、旧来の斉一論はより多くの批判に直面しています。
天変地異説の一番の問題点は、それを検証する実験ができないということです。宇宙空間をさまよう彗星とか極移動、あるいは群れをなして飛来する小惑星など、想像しうるものは何でもあるのですが、それらを実証する方法がありません。仮に地球の公転軌道を横切る惑星があって、それによるならば、多くが説明のつく地形があったとしましょう。しかしだからといって、そのようなことが実際に起きたという証拠にはなり得ません。天変地異説が提唱されて以来、想像力たくましい憶説の出されることが際限なく続き、このことが100年以上にわたって、天変地異説が不評をかってきた一つの理由でした。
そうではあっても、天変地異説はこれまで見て来た通り、やはり必要なのです。ただ、憶説を立てる必要はありません。聖書が既に天変地異の原因や性質、結果について明確に記しているからです。ノアの大洪水だけが神の言葉である聖書に記録され描写されている唯一の全世界的天変地異であり、全地球の地質的・地形的激変に関する豊富で信頼すべき証拠なのです。天地創造の三日目に為された、大規模な地質活動(創世記1:9-10)にその可能性があるようにも見えますが、天変地異は創造が「完了された」ものに対する激変であるという性質上、創造時の神による活動とは異なるもので、確かではありません。言うまでもなく、大洪水は実験によって検証できないという点では他の様々な天変地異説と同じですが、実験による確認は必要がないのです。神が御自分の言葉によってそれを記録しておられる以上、それで充分だからです。
実際には、天変地異(カタストロフィ)という用語は大洪水について用いる語として極めて不適切です。地質学的に言って「天変地異」とは、たとえば津波や火山の噴火のように、高いエネルギーが短期間のうちに広範囲に起きる自然現象をさします。使徒ペテロはソドムとゴモラの滅亡を「破滅」(ギリシャ語でカタストロフィ)と呼んでいます(2ペテロ2:6)。しかし大洪水についてはギリシャ語のカタクリスモス(「大変動」)を使っています(2ペテロ2:5)。英語の cataclysm (地殻の激変)はこれを音訳したものです。同様に主イエスは大洪水について「そこへ洪水(カタクリスモス)が襲ってきて、彼らをことごとく滅ぼした」(ルカ17:27)と言っています。この単語は決して大河の洪水やその他の地質的異変について用いられることはなく、ノアの大洪水についてだけ用いられるのです。
このように、聖書の大洪水は地方の川の氾濫といった局地的な意味のできごとをさすのではなく、世界規模の壊滅的洪水であって、それが大洪水以前の秩序を完全に破壊したのです。真の枠組みは斉一説でも異変説でもなく、天変地異説なのです。
実にこの事実によってペテロは斉一説を論駁しているのですが、それは彼等が天変地異を意識的に無視している提唱者だからなのです(2ペテロ3:5)。地球規模の大洪水があったということは聖書が明確に証言していることであり、それは世界中の堆積層に埋められている化石によって証拠づけられています。これらのことによって、進化論的斉一論が主張するような、万物は依然進化の途上にある、との説明は誤った世界観であることが分かるのです(地質歴史学の聖書的枠組みの詳細については、次の本を参照:John C. Whitcomb and Henry M. Morris. The Genesis Flood (Nutley, N.J.: Prespyterian and Reformed, 1961)。
沈殿層
地殻の地質的形成の主要因が大洪水であるならば、聖書的証拠だけでなく、物質的証拠があるはずです。地球上の堆積岩床のほとんどは、特にそれが化石を含むので、進化論的地質年代システムの根拠になっているのですが、実は水による浸食や運搬、堆積の証拠を提供するのです。事実、このようなわけで、それらは堆積岩と呼ばれているのです。それだけでなく、今や進化論的地質学者にさえも広く認められているのですが、これらは急速な堆積があった証拠を示しており、それも静的な水による堆積ではなく、洪水流によるものであるということの自明の証拠なのです。のちほど述べますが、これらの巨大な堆積岩床は、本質的に同時代の継続的堆積によるものであって、長い静的時間によって断続的に為された堆積の結果ではないことの強力な証拠を示しています。
これらの証拠を十分に評価するには、陸水学と層位学の見識が必要です。現代の水力エンジニアと陸水学者たちは、広範囲にわたる理論的で検証的な実地調査を水流や沈殿運搬についておこなってきましたが、その研究は地層の真の性質に関する貴重な洞察を提供しています。特に驚くべきことでもないのですが、それらは聖書の大洪水の記録と一致していると共に、伝統的な斉一論とは全く符合していないのです。
陸水学(hydrology)は地球の天然水の現象やその分布、特に降雨や河川、地下水の形態に関する科学です。他方で水力学(hydraulics)は水力や水速、摩擦抵抗といった流体に関する学問です。地球上の天然水が果たす重要な働きは浸食・運搬と沈殿・堆積です。堆積作用が河川流路の形成と発達を左右しているのです。川は水をその淵源である海に戻しているだけでなく、流域の浸食による大量の土砂を氾濫原や河口近くのデルタ地帯に堆積します。デルタの堆積物は海の波や海岸の潮の作用によって徐々に浸食され最終的には大陸棚に落ち着くことになります。このようにして陸地表面は徐々に削られ、海洋底に堆積するのです。
これらの堆積プロセスは地質学者や水力技術者にとって非常に重要です。ほとんどの地質過程には水が何らかの形で関っていますが、堆積というプロセスがとりわけ重要です。なぜなら、地球上の地表は、それが未だ柔らかいか若しくは固い岩石となっているかの違いはあっても、ほとんどが堆積層によって成り立っているからです。従って地層の形成や現象を理解説明するには、地質学者は堆積過程について広範囲の理解を持っていなければなりません。
水力技術者にとって、そうした知識は緊急で実務的な必要性があります。その関心事は運河や貯水池、港湾の沈泥上昇、運河沿いの構造物の堅牢性、貴重な土地の浸食、土手の浸食や沖積性河川による水路上昇、その他の現実的で経費のかかる諸問題ですが、こうした事柄が水流による堆積に関連しており、構造物や流路の水力学的設計に関係しているのです。
従って水力技術者達は過去半世紀にわたって、堆積のプロセスに関する集中的な実験と分析的研究を行なってきました。これらの現象は極めて複雑ですが、多くのことが明らかになってきており、今後もそれが続いてゆくでしょう。
明らかになっていることは、現在陸地になっている部分の29%は、かつて水に覆われていたのであり、地表の大部分の岩は元来、流水によって据えられたということです。岩石層は通例、火成岩・変成岩・堆積岩に分類されますが、堆積岩は元々その内容物が水によって運ばれ沈殿・堆積したものです。ほとんどの地表の岩石が堆積岩であることは極めて重要なことです。「比率からすれば、地殻中の堆積岩は火成岩の約十分の一程度であるが、地球表面の岩石ということになると、堆積岩ないし堆積層は地表の四分の三を覆っている。[James H. Zumberge, Elements of Geology, 2nd.ed. (New York: John Wiley and Sons, 1963), p.44)
さらに地表面の火成岩の下には堆積岩があって、その上に火山の噴火や地溝の噴出物が流れ出したのです。同様にして地表の変成岩の多くがかつては堆積岩だったことを表しています(例:大理石は石灰岩が変成を受けたもの)。
地球表面を覆っていた水は、明らかに岩石の形成自体のみならず、地球表面の地形に極めて大きな影響をもっていました。問題はその堆積プロセスが緩慢だったのか、急速だったのか、そしてそれは断続的だったのかということで、これが進化論的斉一論と聖書的天変地異論の間の伝統的論争点だったのです。
たとえば(実はこれこそが当面の議論にとって最もうってつけな例なのですが)、沈殿物の浸食・運搬というプロセスは極めて緩慢な場合もありますが、非常に急速な場合もあるのです。沈殿速度に影響する要素には様々なものがあり、以下は必ずしも網羅的ではないものの、その主要なものです:
1.水流的要素
水路の傾斜、形態、大きさ、水量、河床や河岸の粗さ、水流変化の度合、
水温など。
2.地形的要素
流域や傾斜地の形態と大きさ、排水性、土壌の性質とその植性、支流網と
伏流水の状況など。
3.気象的要素
大雨の頻度とその激しさ、気流の方向や降水の継続時間。
4.沈殿的要素
その規模、形態、変化度、特に重量、さらに運搬されてきた沈殿物の化学
的特性など。
このうえに更にその他の要素を加えようと思えばできるのですが、このリストだけによっても、沈殿速度の平均値を定めようなどということの不毛さが分かります。まして地殻の堆積層の膨大さをそれによって計算し、何億年という年代をはじきだそうとすることも同様に不毛なのです。岩床の形成が天変地異を含む急速なものであれ、あるいは何百万年もかかった緩慢なものであれ、普遍的な自然法則に合致するような合理的理由を岩床そのものは演繹的には提示し得ないのです。
しかし、ある堆積層があれば、その特性を調べて帰納することは原理的に可能なはずだと考える人もいることでしょう。つまり、(1)堆積層の材料のルーツとなった被浸食地域の特性や、(2)運搬した水流の勢いと特質、(3)沈殿地域の特性と範囲などを調べることです。しかし実際には上述の通り、現象に関わった変数があまりに多いので、どのような推定も確実性からほど遠いのです。
沈殿物の運搬に関する研究は、実験室の人工水路を使って数限りなく行われて来ましたし、それよりは数が少ないものの実際の水路を使ったものも行われてきました。これらを通して多くの公式が導き出され現実の問題に適用されて、かなりの成果をおさめてきました。こうした公式のうち、最も単純なものの一つは次のようなものです:
1.36WV4n3
Gs=━━━━━━━
K3d1・5D(1015)
この公式でGsは水流の所与の地点で毎秒運ばれて来た沈殿物の総重量を表しています。Wは水流の幅を、Vは1秒あたりの流速を、そしてnは流路の粗さを表わす係数で、水流の抵抗値を表しています。水深はDで、沈殿物の直径はdです。水温は水の静的粘度に関係し、Kで測られます。Kやnの典型的な値はそれぞれ毎秒約0.00001平方フィートと0.035平方フィートですが、その変化の幅は広いのです。
この公式があてはまるのは、水路が均一な場合だけです。つまり、水速が一定で沈殿物のほとんどが均一な粒子の砂からなる場合だけです。こうした限定つきであったとしても、おおまかな数値が出せるに過ぎないのです。多くの公式によって浮遊沈殿物抵抗やサルテーション抵抗(砂や小石が跳ね飛んで流水に及ぼす抵抗)、河床抵抗を割り出そうと試みられています。また水速や他の要因にもよるのですが、河床上の砂丘を構成する素材は変化しうるので、水流への抵抗が変わり、影響を及ぼします。
水路という問題は複合的で、なにかの要素が変わればそれに伴って変化します。合流地点や水速、水路の粗さ、あるいは沈殿物が様々な大きさのものからなっているならば、沈殿物の搬送値という非常に正確さを要するものの算出はほとんど不可能になってしまい、せいぜい言えるとすれば、沈殿があるか洗い流しがあるか程度のことになります。
また均衡を破るような条件が存在すれば、計算は必然的にさらに複雑なものになります。つまり堆積材料が単に運搬されるのでなく、浸食されたり沈殿したりする場合です。このようにして極めて明らかなことは沈殿のプロセスと速さは、それがどんなに数量的に真実に見えても、厳密なものとは程遠く、たとえ現在の環境においてもそうなのです。
とは言え、上述の公式から一つの非常に重要な推論を導き出すことができます。つまり、変数のうちのどれかひとつ(たとえば、流速)が変化すれば、沈殿量も変化するということ、換言すれば、その沈殿層の堆積は終了し、別な層の形成が始まるということを意味します。このようにして、ある地層が幾つかの他と共通する層を含むという場合、個々の地層は一様な沈殿プロセスのあったことを示していることになるので、流れの変数が一定だったことを示しています。しかし、実際の流水状況において、そうした同一条件の継続ということは、通常、数分か数時間であって、すぐに変数が変わってしまいます。結局、個々の地層はおそらく数分か数時間のうちに形成されたものだということになります。連続する地層の構造や構成に類似平行関係が見られる限り、堆積プロセスそのものは明らかに継続的であり、従ってそれはその地層全体がせいぜい数日間のうちに積み重ねられたものだということを意味します。
実際にはすべての地域的地層はかなり少ない数の層からなっており、ここからすべての地域的地層は急速に、つまり天変地異によって形成されたと結論することが妥当なことです。そのようなわけで、現代の地質学者は地殻の巨大な堆積層を説明するために必要な理論として、天変地異説に徐々に戻りつつあるわけなのです。これは確かに地殻の形成に水が関係したということの証しです。
天変地異(カタストロフィ)が水によるものだという他の証拠
水による沈殿という点からの証拠に加えて、地層には天変地異を示すものが他にもたくさんあって、それらは水利現象の技術的で複雑な証拠よりもずっと明白なものです。後者はより一般的で基礎的ですが、中には際立ったものもあります。そうしたもののうちのいくつかを以下に述べましょう。
化石の墓
よく知られていることですが、特に大きな動物などの生物が死ねば、その死体はすぐに消滅します。それはバクテリアや腐敗プロセスが直ちに作用するからです。しかし地層の岩石にはおびただしい数のあらゆる種類にわたる動植物が埋められており、しばしば化石の「墓場」とも言うべき何千、いや何万もの生物が折り重なって地層に押しつぶされているのが発見されています。何世紀にもわたって、世界中で膨大な量の化石が発見されてきたにもかかわらず、今なお化石の「墓場」は発見され続けているのです。
こうした現象は堆積とそれに続く石化が急激に起きたことによるものに違いないと認めることが科学的道理にかなったことです。そうでなければ、それらは決して保存されなかったはずです。そしてこうした化石の墓場のほとんどは水による堆積層に埋められている以上、これらは天変地異が水によるものだったとの明らかな証拠なのです。
複数層にまたがる化石
成層(つまり、地層が層をなしていること)は堆積岩に一般的な特性です。上述したように、堆積層はおもに継続的で一定の水流条件下での沈殿により形成されます。その堆積が停止し、次の沈殿までしばらくの間がある場合、両者の間には明確な境界(実は前の層の表面なのです)が目視できます。識別できる層の違いは流速や水の特性の変化によっても起きます。今日発見される典型的な堆積岩は多数の「層」からなるものであって、ほとんどの化石はそうした地層に発見されているのです。動植物の大型化石[N.A.Rupke, "Prolegomena to a Study of Cataclysmal Sedimentation?" (Creation Research Society Quarterly 3, no.1, May,1966), p.16-37]が発見されることも稀ではなく、特に厚さが6メートル以上もの複数の地層にまたがった木の幹の化石もあります。オランダの地質学者N.A.ルプケはこれらを「複層化石」と呼ぶことを提唱し、こうした現象の数多くの実例について論文を書いています(図2参照)。
<図2「複層化石」>
急速な沈殿堆積を示す明らかな証拠の一つが、頻繁に発見される複層化石(つまり、多数の連続的地層を観入する化石)です。たとえば、多数の石炭層を貫通する複層化石がはっきり示しているのは、進化論者が主張しているような、石炭層は泥池のピート沈殿槽がゆっくりと堆積していって形成されたもの、ということが誤りであるということです。
こうしたタイプの化石が急激な埋没によって起きたことは疑いがありません。そうでなかったなら、そのまわりに地層が積み重なってゆく時に化石が風化されずに保存されているはずがありません。そしてこうした複層化石を埋蔵した地層は外観や構成物という点で他の地層と全く異ならない以上、堆積速度という点でも特に違いがなかったということが明らかです。
束の間の痕跡
急速な沈殿を示すもう一つの証拠はルプケが「束の間の痕跡」と呼んでいる残存物です。これらの組成物は特殊な化石であり、元々は直前の沈殿層表面に一時的についた痕跡のようなものだったのです。こうしたもののうちにはさざ波の跡とか雨滴の跡、虫の這った跡、あるいは鳥や爬虫類の足跡などがあります。
常識的に見ても分かるのですが、こうしたこわれやすいものは一旦できても、次の風や雨とか、その後の風化・堆積によってたちまちの内になくなってしまうものです。それでも保存される唯一の場合というのは、異常に急速な埋没(しかも浸食されずに)と異常に急速な石化が起きた場合だけです。
仮にそのような現象が今現在起きていたとしても、これがその例だと言って示すことはたとえ不可能ではないまでも、実際上困難なことでしょう。濁流による突然の埋没ということがよく提唱されます。たとえば、ドイツのフランクフルト大学地質学部のアドルフ・ザイラッヒャーは次のように言っています:「フライシュ砂岩の後期堆積層底部の擦痕は薄い岩床にのみ起きるもので、それも個々の種類固有の厚さが限度である。このことは個々の河床が瞬時に堆積したという証拠であって、濁流理論が提唱している通りである。底部擦痕の大部分は堆積前の泥穴が洗い出されたものと、泥流によって砂がかたどったものなのである。このようにして、異常なタイプの浸食がすべての泥流沈殿に先立ったに違いない」[A.Seilacher, "Paleontological Studies on Turbidite Sedimentation and Erosion," (Journal of Geology 70: Mar.1962), p.227]。
注目すべき事実はこのようなタイプの束の間の痕跡は古代の堆積岩に非常に多く、実際上は最も古代のものを含む、いわゆる地質時代全般にわたって発見されるということです。しかもそれらは現代に発見される時は一様に鮮やかであり、それは原生代であろうと、第三紀あるいはその間のどの地質時代であろうと、変わりがないのです。こうした痕跡とその保存の説明となりうるものは圧倒的に天変地異的な堆積現象だけなのです。
柔らかい部分の保存
おびただしい例が知られているのは、化石が残っているのが石化したものとか、鋳型のようになっているのではなく、実際の柔らかい組織が保存されてきている場合です。これは極めて「古代」の地層においても事実であり、そうした化石はしばしば数多くかたまって発見されます。こうした堆積物は単にそれが沈殿による急速な埋没を物語るばかりではなく、何百万年もの間、腐敗や浸食を受けずに残っていたなどという説を到底信じ難いものにします。
成層現象
堆積層に含まれている化石が天変地異による堆積の存在の必要性を示しているだけでなく、堆積層自体がそれを示しています。すでに述べたように、地球表面の大部分は堆積層や堆積岩でおおおわれており、それらはもともと水面下で沈殿したものでした。このこと自体こそ地球が大水によっておおわれていたということの最たる証拠なのです。現代の状況においてさえ、ほとんどの沈殿堆積は、短期集中的氾濫の結果であって、緩慢で均一な沈殿によるのではありません。
実験上証明されていることは、典型的な沈殿堆積層は極めて急速に形成されうるということです。これはハーバード大学のアラン・ジョプリンの研究にありますが、彼は三角州タイプの堆積を実験室の人工水路を使って長期にわたって行い、1万3千年前に形成されたと思われる小型三角州の分析結果に適用しました。彼の結論は次のようなものです:「従って結論として言えることは、三角州全体の堆積に要する時間はせいぜい数日である。それは三角州の発達速度と各層の厚さの計算結果に基づいており、各層の平均的堆積所要時間は数分だったに違いない」[Alan V. Jopling, "Some Principles and Techniques Used in Reconstructing the Hydraulic Parameters of Paleo-Flow Regime," (Journal of Sedimentary Petrology 36, Mar.1960), p.34]。
集中的な水の活動によるものだということを更に裏付ける証拠は、地層の多くの堆積層が小石やその混成物どころか、玉石さえも含んでいるという事実です。同様に頻繁に見られる「河床交差」現象も流水方向の急速な変化を示しています。
沖積谷
実際上、現代の河川はかつて、はるかに多い水量で谷を流れていました。このことは谷によく見られる高所にある昔の川をあらわす段丘によって分かるだけでなく、氾濫原というかつての流路を埋め尽くしている膨大な量の砂や石によっても分かるのです。
ウィスコンシン州のドリフトレス・エリアにある蛇行渓谷の表層下を屈折地震計によって探査した結果、大きな埋没型流路であることが分かった。これは以前、螺旋化技術が使われたと判定されたイギリスの河川に類似している。その流路は合流点で非対照であり、谷が曲がっているところで最も深くなっている。合流地域が渇水の時には現在の約25倍の流路だったと思われる [G.H.Dury, "Results of Seismic Explorations of Meandering Valleys," (American Journal of Science 260, Nov.1962), p.691]。
こうしたことは実際上よく見られることです。たとえばミシシッピ渓谷は600フィート(180m)の厚さの氾濫原から成っています。これら全てが示していることは、世界の河川はごく最近に(おそらく大陸棚隆起中か、その後で大洪水の終わりに)膨大な量の水と土砂を運んだということです。
刻まれた蛇行
沖積流によく見られるもう一つの特徴は蛇行現象です。蛇行の原因とメカニズムについては多くの分析や実験研究が行われてきましたが、いずれも部分的にしか説明できていません。しかし通説となっているのは、流路が蛇行するためには勾配が比較的ゆるやかであって河岸が浸食され易いことです。もし勾配が急であって河岸が堅ければ、浸食はもっぱら河床に起こり、谷が形成されることになります。
従って最も注目すべきなのは、高原や山岳地帯の深い峡谷に刻まれている入り組んだ蛇行パターンです。それらは月並みな水力学による説明に対して、あたかも挑戦状をつきつけているようであり、かつ地質学者の説(例えば重層蛇行説)も水力学を忘れたもののように見えます。
刻まれた蛇行は明らかにある種の激変に起源があることを示しています。こうした地層の形成にふさわしい条件を備えた現実的なモデルになりうると思われるのは、大洪水の後で隆起した際に広く水平な堆積層が、まだ比較的やわらかで浸食を受けやすい時に、隆起プロセス中に大きな亀裂ができたということです。その初めの亀裂が急速に拡大深化し、隆起に伴って膨大な量の水が急速に排水される際に、現在の蛇行峡谷となったのです。
堆積が1回の出来事である証拠
もちろん、以上に掲げたものが、水による天変地異を示す証拠としての完全なリストではありませんが、その代表的なものと言えるでしょう。火成岩や変成岩も同様に急速な形成を示す多くの証拠を提供します。
一般的に言って、現在知られている大部分(というよりはすべての)地層の特性を解釈する枠組みにふさわしいのは、天変地異説なのです。他方の斉一説はそれらのいずれをも十分に説明するには全く不適切なものに思われます。
しかしここに一つの問題があります。今日多くの地質学者が様々な地質現象を説明するものとして、水による天変地異という考え方の有効性を認めるようになってきてはいるのですが、なおかつそれが一回の大洪水という聖書に書かれているような出来事によるものだという考えには根強い抵抗があります。地質歴史学者が依然として好むのは、斉一説と地質年代という一般的枠組みであり、その枠組みの中で集中的で大規模な複数の洪水とか、他の局地的激変を認めようとするのです。
このようにして問題は前述したものを含む多くの天変地異的堆積の証拠が一つの大洪水によって起きたのか、それとも数知れない小さな激変によるのかということになります。
もしそれが宗教的意味の為ではなく、単に実際の物理的データに関する論理的説明の探究のためだけだとしたら、オッカムのカミソリの原理の適用は直ちに、一回の大激変の方に理があるということになるでしょう。(訳注:ウィリアム・オッカムは中世の神学者・論理学者で、彼の有名な原理「オッカムの剃刀」は「必要なしに実在を多数化してはならぬ」という形で知られる思考節約の原理。本来観察された事実、論理的自明性、神的啓示など十分な根拠なしにはいかなる命題も主張してはならないことを規定して、不必要な仮説の増殖に警告を発している)。
これに対して、多数の地質的天変地異が世界中で、またすべての地質時代において存在したと主張し、それによって多くの天変地異の証拠を充分説明できるとすることは、明らかに聖書の大洪水記録に反し、歴史の進化論的解釈の肩をもつことであって、それ自体が強い信条的偏見を示しているように思われます。そのうえに、こうした多くの天変地異は現代世界で観察することができるどのようなものよりもずっと大規模だったとか、斉一説は実験則上どのような実質的枠組みとしても不適切であるとするに至っては、何をか言わんやです。
天変地異が水によるものであるという証拠は、上述した通り様々ありますが(化石の墓場、多層化石、束の間の痕跡、その他)、これらは地層全体にわたって多かれ少なかれどこでも普通に見られるものです。地球の進化プロセスという前提に立って推測されている気候変動や、地学的時代に対応して想定されているような地質時代全体における特徴的天変地異が進行的に変化していったというような証拠は存在しないのです。原生代の堆積層も第三紀(あるいはその他)の堆積層も物理的特性は本質的に同じであり、唯一の違いといえば、化石の集まりかた、特にその中に含まれている標準化石が違うという点です。
そしてもちろん、化石の集まり方そのものは進化論的斉一論よりも、大洪水によるほうがより良く説明がつきます。化石類は進化論によれば、地質年代の経過によってより高度なものになってゆくべきはずのものですが、この解釈は事実と食い違っており、すべての主要生物相互間には大きなギャップがあるのです。そしてそれは現代の全動植物間にあるギャップと本質的に同じです。
化石が一般的に類似サイズや形のものが類別されたように集まって発見されるという事実こそ、大洪水による結果だと推定されることであって、逆巻く水が効果的な「並べ替え」の働きをしたからなのです。ハーバード大学における谷川の研究でジョプリンが発見したことは、たとえ流れが一定でむらのないものであり、かつ運搬される堆積物が最初はランダムに混濁したものであったとしても、流れはそれらを並べ替えてしまうということでした。「類別ということは不可避的に発生するものであり、それは堆積物の運搬がほとんど一様な条件下であって、様々なサイズの沈殿物が当初はまったく混濁していた場合であってもそうなのである。この類別化は河床が平面であろうと波形あるいは砂地であろうと発生し、流れに対して縦横の両方向に起きることがわかっている」[Alan V. Jopling, "Laboratory Study of Sorting Processes Related to Flow Separation," (Journal of Geophysical Research 69, Aug.15,1964)]。
この並べ替え作用は基本的には流水の「上昇と引っ張り」力の大きさに起因するもので、この力のかかりかたが水中物のサイズや形に関係しているのです。もちろん同様のことが水の中を縦方向に落ちる物にもあてはまるので、形の単純なもの(したがって、より「原型」に近いと考えられるもの)の方が流速が弱まる所ですぐに集まって、形の複雑なものよりも深みに堆積することになります。この傾向がさらに強まるのは、いわゆる「高等」生物よりも、形の単純な生物(たとえば貝類)のほうにおいてでしょう。
その他の事柄が同じであれば、単純なもののほうがより低い所に住むので、それらが下方に埋まるということが考えられ、さらに動物の動きまわる能力はその発達度とどちらかというと関係しているので、発達した動物ほどより長い時間、埋没を免れるということになるでしょう。
これらの要素すべては現在発見される洪水堆積層中に保存されている化石順序の要因となったのでしょう。従ってここから進化論を引き出すことは明らかに不適切なのです。
これら三つ ── つまり、水力学的要素、環境的要素、生理学的要素 ── は絶対的なものというよりは、統計的なものであることはもちろんですが、これまで発見されてきた通常の順序にはたくさんの例外があるということは特に驚くべきことではありません。しかしそれらはかえって進化論者にとっては当惑させるものでしょう。なぜなら化石が逆転した順序で出てくることは進化論に反することであり、地質年代を全くくつがえすことになるからです。
進化論的推論に特異なのは、こうした変則や矛盾がありながら、進化の基本的仮説に対して決して疑問が提示されないことです。その結果、さらに多くの仮説が倍加され、化石を含む地層が逆転しているのは、地球の大変動によった可能性があると説明されるのです。広範囲にわたる水平的な「欠陥貫入」によって、非常に厚い堆積層が押し上げられ、次に周辺地域に水平的に移されたのだというのがメカニズムについての典型的な説明であって、これが「古代の」化石を含む地層が「最近の」地層の上に発見される多くの場合にあてはめられているのです。
ちょっと風変わりなのは、もう一つ別な水力学的原理を用いて、そのような運動がどのようにして可能なのかを説明していることです。なぜなら、良く知られている通り、地滑りはたとえそれが十分な水分を含んでいる場合であっても、通例、地滑りする地層構造の統合性を完全に破壊することなくしては起き得ないからです。現在の通説となっている説は、貫入した塊というのは、内部の異常に高い流体圧力により、貫入平面に沿って「浮遊」していたというものです。
これらの圧力が実際に作用を及ぼすためには、通常の地下水以上にかなりの高圧でなければならず、そうとすれば堆積層が形成された時にその割れ目に圧縮して閉じこめられたことによるのではないかと考えられます。つまり最初は堆積層が次第に圧縮と石化を受けるにつれて、土孔に含まれている「遺留水」が閉じこめられて逃げ場を失って圧縮され、その結果その上の巨大な岩の重圧をも跳ね返して浮かせてしまうほどの圧力をもつに至ったと考えられます。
これは実に注目すべき仮説です。貫入した塊の周囲に見られる「封入物」(貫入塊そのものが数百、数千平方マイル以上広がっていることは稀ではない)はそれ自体が非常に弾力性のあるものだったはずで、塊が水平垂直のいずれの方向にも動くことを可能にしながらも、そのプロセスで圧縮水が逃げるのを妨げていたと思われます。この説の説得力ある分析の中でプラットは次のように指摘しています:
明らかに重要な要素は粘土や粘板岩の中に形成される封入物の質である。ほんのわずかでも浸透性があると、それが他と比較すればどんなに効果的にその下の「遺留水」を含む層を封じ込んだとしてでも、やはり漏れが起きてしまう。したがってその岩を「浮かせる」液体の支えが必要だとするならば貫入運動は最後の質量がかかる厚い層の堆積が終わった直後に発生しなければならない。遅すぎれば粘板岩による封入が効いて液もれは起きないことになる。[Lucian B. Platt, "Fruid Pressure in Thrust Fauling, A Corollary," (American Journal of Science 260, Feb. 1962), p.107]。
もちろんプラットが提唱している岩塊の初期浮遊の必要性は、液体が圧力を高めるには圧縮と石化のための長い時間が必要なのではないかということと相反することになります。さらに重要な問題点は貫入活動のあいだ必要な封入剤がどのようにして供給され続けるのかということについては説明されていないことです。
液中浮遊貫入説には最近さらに多くの人々が反対を表明する著作をしています(たとえば、P.L.Guth, K.V.Hodges, and J.H.Willemin, "Limitations on the Role of Pore Pressure in Gravity Gliding," Geological Society of America Bulletin 93, July 1982: p.606-12])。しかしこれ以外に「古い」岩塊が「若い」岩の上に乗っているという現象を説明するメカニズムは考えることができないように思われます。少なくとも巨大スケールで見られる世界中の貫入現象に関する限り、アルプスやアパラチア山脈、ロッキー山脈やその大部分、カスケード山脈、その他の世界の大山脈は(いわゆる「地質時代」区分に従う限り)この逆転現象だと見られますが、ほかにまだ知られていない天変地異によるのでない限り、これ以外によっては成し得なかったのです。もちろん、聖書や他の証拠が示すように岩石は本質的に同年代だとすれば、問題はないのです。
同時代性を示すもう一つの証拠は変則化石という地質学会の秘密、つまり進化論的なある「地質年代」の化石が他の年代のものと混在して発見されることです。これはかなり一般的な現象なのですが、通常は無視されるか「事後作用」とか「置き換え」の場合であると説明され、その化石が元来堆積したところから何らかの理由で発見された場所まで移動したのだとされるのです。
これは場当たり的な説明ですが、反証することが困難であるため、ほとんどの地質学者を納得させます。なぜなら彼等は標準となっている地質年代に疑義をさしはさみたくないからです。しかし異なった時代の動物の足跡化石が同時に発見されると、この種の説明は瓦解し、地質学者達は地質年代体系の誤りを認めまいとして根拠もなく、捏造だとの主張に訴えることになります。
これが有名なパルクシー川の足跡です。この場合ではおびただしい数の恐竜と人間の足跡が「白亜紀」の石灰岩の同じ地層上に発掘されていますが、ほとんどの地質学者は理論上ありえないことだとして、証拠として認めることを拒絶しています。というのは人類と恐竜は標準的な年代表によれば7000万年の隔たりがあるとされているからです。しかし、足跡はそこに確かに存在していて、明らかに本物であり、人間と恐竜は同時に生活していたことを結論づけています(この証拠の詳細な検討については次を参照:John D. Morris, Tracking Those Incredible Dinosaurs and the People Who Knew Them (San Diego: Creation-Life, 1980), pp.250. この本が著わされた後、同じ場所から更に他の人間の足跡が発掘されている)。
これまで見て来たように、岩石の地質年代を決定するための真に客観的な手段は存在しません。つまり、地質年代は化石によって推定されるのですが、化石はその仮定される進化の段階を根拠にしています。ところが進化の証拠とされるのは唯一、地質時代中にあったとされる進化の順位を示す化石なのです。このような循環論法と畳語法は変則化石や貫入のような逆転地層などによって疑義を生じます。
それだけではなく、どんな岩石や鉱物、金属、また石炭や石油などもすべての時代の岩の中に発見されているのです。硬度や密度という点では多くの古い岩石は新しく見えるし、多くの新しい岩石も古く見えます。地層の年代順という点ではあらゆる組み合わせで見つかっており、いずれかの年代層が欠けているケースも世界中の様々な地方の地層で発見されています。
言い換えれば、ある岩石形成層が他のものより古いとか新しいとかを明確に判定する方法は存在しないということなのです。放射能年代測定法が多くの欠点を持っていることは知られており、実に頻繁に地質年代と食い違うのですが、そういう場合には地質年代の方が優先されます(結局それは進化論が基本になっています)。従ってほかの方法で年代決定できたとしても、すべての岩石が同時代のものであり得るし、全てが同時に形成されたということもありうるのです。要するに、各地層はある種の地質的天変地異によって急速に形成されたのですから、それらは皆同じ世界的規模の大洪水の異なった相において形成され得たのです。
その意味するところが決定的に確実となるのは、世界中の地層という記録全体には一致性があり、不一致点があるとすればその最基底部や洪積世および洪水後の地域的沈殿物ぐらいだということが明らかにされたからです。不一致性というのは相互に似通っていない地層をもつ二つの地質構造が接している浸食表面です。従ってそれはその地質構造の上部と下部の間に何らかの時間的ギャップがあるということをあらわしているのです(図3参照)。
<図3「堆積層の世界的連続性」>
世界的に見れば、浸食面や沈殿プロセスの阻害証拠といった時間的ギャップの不整合生は存在しないので、地質年代上で世界的な時間のギャップはありません。それぞれの地層や地質構造は休息に形成されたのである以上、地層全体は連続的で急速な水による岩石の堆積によって地殻が形成されたことを表しています。
こうした不一致性があるために「地質年代体系」維持しようとして、「挿入的堆積層」の時代間に長年月をおいて、いわゆる地質時代を形成するわけです。しかし世界的には一致性があるので化石を含む地層には世界的に見れば時間のギャップはないのです。最後に地層のすべての部分は少なくとも地域的な激変を表しており、かつ世界的には時間のギャップがないのですから、すべての地域的な激変は関連があり連続的であるに違いありません。
だから世界のどこの地層でもいいのですが、誰かがその最下層からはじめて地表までたどってゆき、何も問題がなかったとします。地域的な不整合性に遭遇したときはいつでも、彼はただその水平方向のどこか他の地域で、上方に整合的につながっている所に移り、そのまま上昇していったとしましょう。このようなことはしようと思えばいつでもできるのです。なぜなら、どんな地域的不整合性も地球大に広がってはいないのですから。そのようにたどってゆくならば、堆積プロセスは連続的となり、また個々の地質構造は天変地異の産物なのですから、全体は時間的に中断のない一連の天変地異を表しているに違いありません。同様の方法は地層基底部のどの地点からもはじめることができます。このようにして、地質という記録全体は「地域的」天変地異の広範囲にわたる複合状態を表しており、すべては互いに関連し合って連続的であるということになります。使徒ペテロは「その時の世界は、御言により水でおおわれて滅んでしまった」(2ペテロ3:6)と言っていますが、こうした全体はペテロが言ったような世界規模の大洪水をなかったことにしてしまいます。
自明のことですが、非常に広範囲な分野としての聖書的地質学でも、子供向けにわずか一章にまとめようと思えば可能でしょう。実際上の地質データやプロセスは聖書的創造論者にとっても進化論的斉一論者にとっても同一ですが、そうしたデータを歴史的文脈の中で解釈することにおいては非常に異なっています。地質学はこの100年間、進化論と地質年代に全く傾斜し続けて来たのであり、また地質データも膨大かつ多様であるため、これらの全データを真の聖書的枠組み(つまり、最近の創造論と全地球的大洪水)で再編成することは、多くの創造論に立つ科学者による、とてつもない研究と調査を要することでしょう。他方で、この広範なテーマについての更に詳細な論述をしているものとして、ジョン・C・ホワイトコム博士と私の共著 The Genesis Flood (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1961, 518pp.)があります。また大洪水と地質学に関するさまざまな観点からの重要な記事が数多く掲載されているものとしては Creation Research Society Quarterly があり、1964年以来多くの書籍とともに出版され続けています。
解決されるべき問題はたくさん残っていますが、本章で概略述べたことによって、少なくとも地球の歴史についての聖書モデルの方がこれまで進化論的地質学が提示した標準的モデルよりもはるかに地質的事実に適合するということが示されたと思います。今後の一層の調査研究により、残りの問題もやがて聖書モデルの枠内に答えが見い出されることでしょう。