国民の祝日:昭和の日
~ 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす 日~
4月29日は『昭和の日』でした。国民の祝日に関する法律が1948年(昭和23年)に制定されると、それまで、『天長節』として歴代の天皇の誕生日が祝われていたのを、昭和天皇の誕生日4月29日を天皇誕生日として祝うようになりました。※ちなみに、1948年は私の生まれた時でもあります。(全く関係ない事ですが)
それから、1988年昭和天皇の崩御に伴い1989年から4月29日は『みどりの日』となり、「大自然の恩恵に感謝する日」となって、祝日として続きました。
そして、2006年まで18年間続いた『みどりの日』は、2007年に現在の『昭和の日』と改名されて、現在に至ります。『昭和の日』は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」と祝日法に定められています。一方、『みどりの日』も5月4日に移動して、今も祝日として存続しています。
今年は昭和100年に当たります。確かに、昭和の時代に生きた私たちにとっては激動の時代を生き抜いてきたように思います。
私の小さい頃、僻地の屋久島で育ちましたが、幼少期は電気もガスも、水道もない時代でした。ランプの火屋を磨いていて割ってしまった記憶や、小学生時代には毎日近所の友達と5~6人集まって学校まで水を汲みに行っていたことなど思い出します。
つい先日、小学生の頃一緒に小学校まで水汲みに行っていた弟が、私たちの出身校、『屋久島町立宮浦小学校開校150周年記念誌』を購入して送ってくれました。それを見て初めて、母校が150周年だったことを知りました。
今は、鉄筋コンクリ-ト2階建てで、随分立派な校舎になっていて、びっくりしました。私たちの時代は、平屋建ての木造校舎で、職員室の前の校庭には池があり、そこに浮き草・ホテイアオイが沢山浮いていたのをよく覚えています。
また、学校に水道が敷かれる前は、山から引いてきた水が四角いコンクリートの水槽の中に入り、それの所々に小さな穴が開いていて、そこから常にちょろちょろ水が流れ出ていて、子供たちは皆そこに口をつけて飲んでいました。
そして、その横には大きなゴムの木があったのと、校門を入ったところには築山があって学校の象徴のようになっていましたが、残念ながらその当時の写真は残っていなかったようです。しかし、昔の町の様子が映っていて、当時を懐かしく思い出しました。
ただ、弟の手紙には今年の新入生が19人とのことでした。私たちの頃は1クラス40人ほどの2クラスでした。校舎は立派になったけど、我が母校にも少子化の波が押し寄せて来ているんだなあと思いました。
また、私たちの小学時代は、今に比べると貧しく質素な生活しかできませんでしたが、皆がそうだったので、貧しさや惨めさを感じることなく、毎日満足して楽しく生きていたように思います。
今の子供たちは素敵な家に住んで、良い洋服を着て、美味しいものを食べて贅沢に過ごしているように思います。しかし、幸せは物質的な豊かさにあるのではなく、心の豊かさにあるように思います。心の豊かさを求めて参りましょう。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んでおられることです。Ⅰテサロニケ5:16~18
わずかな物を持っていて【主】を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのにまさる。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのにまさる。箴言15:16~17
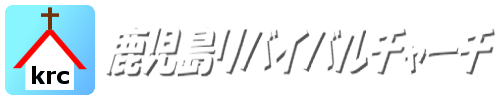
No Response to “国民の祝日:昭和の日”