誠実な努力で身に着ける職人技 川下真理
~小さなことを誠実に行うことが大切~
色々な国で町を歩き回るのはとても楽しいことですが、特に旅の後半になると、出発時にはほとんど空だったバックパックが、おみやげな等でぱんぱんになってきます。時には10キロ近い重量になることもありますが、不思議なことに、それを背負って猛暑の真昼に何時間も何キロも歩いても全く疲れを感じないことが多いです。むしろ、見たことのないものを見たり、慣れない匂いを嗅いだり、衝撃の光景に出くわしたりするたびにエネルギー残量が増えていくような気さえします。
逆に、常に動き回っていないといけないということはなく、心ひかれるものがあると、ただひたすらそれを見ているのも好きな部分もあります。
海辺で釣りをしているおじさんたちと並んで砂浜に座り、何が釣れるのか、おじさんたちが何をしゃべっているのか(言葉が通じないので想像ですが)見守ったり、れんがを割りながら建物の玄関の階段を作り上げていくところを見学したり、高層ビル表面の作業のため地上にロープを投げてものを受け渡す明らかに効率の悪い方法をあきれてながめたり、道端で重機が敷石を掘り起こしているまわりで作業員たちが片手で何か食べながらうろうろしている信じられない安全管理のレベルの工事現場で立ち止まったり、野良犬?と一緒に座ってじっとまちを見ていたり…。
挙げるときりがありませんが、こういう話をすると、一体何が楽しいのかわからないというご意見をいただくこともあります。でも、慣れた手つきでたこやきを作る屋台の人を見ていると楽しいとか、焚火の音や川のせせらぎにただ耳を預けてぼんやりするのが好きというかたは多いのではないでしょうか。私にとってはそういう感覚に近いような気がします。
ところで、上記のような旅の途中の立ち止まり時間のなかでも、特に印象的だったものがあります。その日は有名な灯台のある半島の先まで歩いてみた帰り道で、あちこちに遠回りをした結果、時刻は午後の後半に差し掛かっていたと思います。いつものようにインターネットは使えない状態で地図も見られないため、できれば暗くなる前に、少なくとも人の多い住宅街のあたりまでは下りたほうがいいと思い、少し急ぎ足で坂道を下りていました。すると道端の木陰の向こうに一軒の民家らしい建物が見え、一人の作業員のおじさんがそこで何かしていました。おじさんのやっていることが目に入った途端、思わず足を止めました。
おじさんはいわゆる左官屋さんのようなことをしていて、建物の壁をやわらかい粘土のようなもので仕上げているところでした。コテのような道具を使って、壁に粘土みたいな塊をくっつけては器用にならしていきます。バケツの中に粘土がなくなると、粉の袋を開け、液体の量を調整しながら別の道具で混ぜ、また壁作りです。そんな作業を20分以上は見学した結果、私もやり方を覚えたような気がしてやってみたくなりました。おじさんのところに歩いていくと、なんだろうという顔をされましたが、私が興味津々でずっと眺めている間も気づいている様子だったので、そこまで驚いてはいませんでした。相手の言葉は話せないので、英語と身振りで「私もこれやりたい」と伝えると、特に反対もせず道具を渡してくれました。嬉々としておじさんのやっていたように壁を塗ろうとしますが全然うまくいきません。見ていて覚えた気になるのと実際に作業してみるのとでは、案の定大違いです。
それでも、「きっと私だって何度かやれば…!」と諦め悪くしばらく苦戦しましたが、見学の成果は一向に上がりませんでした。傍らで見ていたおじさんに、「やっぱりできない」と道具を返すと、私が作り上げたでこぼこの壁が数回のコテさばきで跡形もなくなめらかになりました。
特に愛想のいいおじさんでもありませんでしたが、日本人ほど愛想よく礼儀正しい人ばかりでもないのには慣れていたので、気にはなりませんでした。お礼に、旅でいつも持ち歩いている知覧茶をあげると、意外にも嬉しそうな顔をしたのでもう一つあげました。
おじさんにとってはいつもの作業だろうし、特別なことではないのでしょうが、きっとこうしてずっと黙々と誠実に仕事をしてきたからこそ身に着けた職人技なのだと思うと、気取らない素朴な態度も含め、あらためて尊敬の念を覚えました。
小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実です。ルカの福音書 16:10
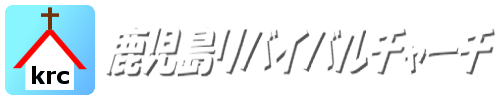
No Response to “誠実な努力で身に着ける職人技 川下真理”